通所介護を中心とした介護業界では、短時間勤務を行うパート職員も多くその勤怠管理への対応が煩雑になっている実情も多いのではないでしょうか。勤務時間の集計であったり勤務時間ごとに異なる法で定められた休憩時間を取れているかなど、細かい集計や管理が必要となります。介護施設向けの勤怠管理システムを導入するとこういった勤務時間の集計や休憩時間の管理を自動化することができます。ここでは通所介護施設などの勤怠管理者や責任者の方向けに、休憩時間のルールを立ち返りつつ、それ他の勤怠電子化のメリットも含めて通所介護施設への勤怠管理システムの導入についてご案内しています。ぜひこの記事を読んで勤怠管理システムの選定に進んでみてください。
1.通所介護施設が抱える勤怠管理の三重苦とは
通所介護施設の運営業務は介護サービスの提供であったり、利用者様とのコミュニケーション、職員のメンタルケアなど多岐にわたります。その中でも特に頭を悩ませるのが、手間とミスが起こり得る毎月の勤怠管理ではないでしょうか。
通所介護は、短時間勤務のパート職員も他の介護サービス業種とよりも多く勤務形態が複雑になりやすいという特性があります。その煩雑さゆえに、多くの施設が勤怠管理の三重苦に直面しています。
1-1.【1つめ】勤務の多様性による「集計のミス」
通所介護施設では、サービス提供時間に合わせて、短時間勤務のパートスタッフが多数勤務しています。午前のみ、午後のみ、また中抜けや変則的な休憩を挟むなど、一人ひとりの勤務時間が日によって、あるいは週によって異なり運用されていることも少なくありません。こういった複雑な勤怠実績を紙のタイムカードやExcelで手作業で集計しようとすると、間違いが発生してしまったり、長く時間がかかってしまうことになります。例えば、「8時45分から13時15分までの勤務」といった細かい時間計算で、1分単位の計算も必要になりそれもミスの要因となってしまいます。また勤怠実績は集計後に給与計算へ回されることが常ですが、このデータの移し替えも何かしら手作業を経て給与計算システムへ入力することになるので、給与計算段階でも転記ミスが起こることもあります。
この手作業による集計作業の負担は、主に管理職や事務担当者に重くのしかかり、本来は現場のマネジメントや経営改善、本来の業務に充てるべき時間を勤怠の処理で消費してしまっています。
1-2.【2つめ】短時間勤務だからこそ難しい「休憩付与の漏れ」
労働基準法には、労働時間に応じた休憩時間の付与義務があります。6時間を1分でも超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
勤務時間が日々変動する短時間勤務のパートスタッフの場合、「今日は6時間ちょうどだから不要」「明日は6時間5分だから45分必要」といった休憩時間管理を、毎月・毎日必要となってきます。このチェックが漏れてしまうと、意図せず法定の休憩付与義務に違反してしまうという、大きなコンプライアンスリスクを抱えることになります。
手作業による勤怠だと短時間勤務が多い場合、実態として休憩時間のフォローが追いつかないこともあるかもしれません。こういった休憩時間の按分(自動的な配分・控除)を手作業で行うことの難しさが、施設運営の大きな課題の1つとなっています。
1-3.【3つめ】法令違反リスクという「経営の重荷」
これらの集計ミスや休憩付与の漏れは、本当に行き着く先は労働基準監督署からの調査が入り是正を求められる、ということになりかねません。日々の煩雑な作業が、気づかぬうちに施設経営のリスクとなってしまいます。
本記事では、この通所介護施設特有の「三重苦」を、介護業界向けの「勤怠管理システム」が効率的に解決できるのかを、具体的な機能と導入効果を交えて解説していきます。
2. 労働法制における休憩時間付与の基本ルール
通所介護施設の勤怠管理で最もリスクが高く、管理を煩雑にしているのが休憩時間です。この休憩時間の管理をシステムに任せる前に、改めてとなりますがまず法律で定められた基本的なルールをここでは確認します。
2-1. 労働時間と休憩時間の法定ルール
労働基準法第34条では、企業が従業員に与えなければならない休憩時間について、明確な基準を設けています。このルールは、正社員かパートタイマーかを問わず、すべての従業員に適用されます。以下の表が休憩時間のルールです
| 労働時間 | 休憩時間の長さ |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間超 1時間以上 | 60分 |
大切なのは、この基準が実労働時間に基づいて適用されるという点です。通所介護施設で働く短時間勤務のパートスタッフの場合、日によって勤務時間が変動するため、管理者はこの「6時間」の壁をシフトと実際を毎日チェックしなければなりません。
例えば、「9:00〜15:00(実働6時間)」の勤務であれば休憩は不要ですが、「9:00〜15:05(実働6時間5分)」の勤務になった瞬間に、45分以上の休憩付与が必須になります。手書きやExcelでの管理では、このわずかな差を見落とし「休憩付与の漏れ」を引き起こしがちなのです。
2-2.「休憩時間の原則」と通所介護の特殊性
休憩時間には、以下の3つの原則があります。
- 途中付与の原則
労働時間の途中に与えなければならない。 - 自由利用の原則
休憩時間を従業員が自由に利用できなければならない。(電話受けや来客対応はさせてはならない) - 一斉付与の原則
原則として休憩時間は従業員に一斉に与えなければならない。(これは例えば昼休憩は全従業員で同じ時間にあたえないといけないというような原則ですが、労使協定で実際には休憩時間をずらして取得できるようになっています)
通所介護施設の場合、一斉付与の原則はシフト制の導入などにより労使協定で免除されていることがほとんどですが、特に「自由利用の原則」と「途中付与の原則」は厳守する必要があります。
短時間勤務のパートスタッフの場合、休憩時間を短く設定したり勤務時間の最後に寄せたりして、その代わりに早く帰宅させたいという意図が生じることもあります。しかし、法律上は労働時間の途中で休憩を与え、その間は業務から完全に解放することが求められます。
2-3.短時間勤務こそシステムによる正確な休憩時間の割り当てが必要
手作業での勤怠管理では、これまでにご紹介した休憩の法定基準をクリアするため手間が生じてしまいます。パートタイマーの毎日変わる勤務時間に対して、労働予定時間に対して休憩時間(45分か60分か)を正確に割り当てる作業が必要になります。
また、企業に義務付けられている法定帳簿でも出勤簿や賃金台帳には休憩時間を記録する必要があります。これは労働時間の一部として見なされていないことを証明するためです。
これらの煩雑な作業を人の手で行う場合、集計担当者(多くは管理者自身)の残業時間を増やすだけでなく、ミスによる法的リスクを常に背負うことに繋がります。次章では、この短時間勤務特有の集計と休憩按分の課題を、勤怠管理システムがどのように解決するのかを具体的に見ていきます。
3.短時間勤務の勤怠課題をシステムでどう解決するか
ここでは短時間勤務の勤怠課題を介護業界向けの勤怠管理システムで解決していけることをご案内いたします。
3-1.【集計課題の解決】複雑な勤務時間も自動で計算
手作業での集計において最も時間を要するのが、日々の勤務時間が異なるパートスタッフの実労働時間の計算です。
勤怠管理システムを導入することで、 1分単位での正確な労働時間計算を行うことが可能です。例えばスタッフがタブレットやICカードで打刻すると、システムは休憩時間を差し引いた実労働時間を1分単位で自動計算し、集計することができます。計算式がシステムに組み込まれているため、手作業でやっていたような「8時45分から13時15分の実労働時間は…」といった計算やExcelの数式調整は無くすことができます。これにより、集計作業を担当していた管理職や事務担当者の残業時間を大幅に削減することができます。特に給与計算の前に集中していた膨大なチェック・修正作業がなくなり、本来のコア業務に時間を充てられるようになります。
3-2.【休憩時間割り当ての課題解決】法令遵守を担保する自動休憩付与機能
第1章で解説した通り、労働基準法の休憩付与ルールは厳格です。短時間勤務のスタッフの勤務時間がわずかに6時間や8時間を超えた際、「休憩付与の漏れ」を防ぐことが最重要課題となります。勤怠管理システムは、この休憩時間の「付与」と「控除」を、実績を追認するのではなく、計画段階で組み込むことで解決します。
①シフト作成段階で法定休憩を自動割当
多くの勤怠管理システムにはシフト作成機能が搭載されています。この機能では、管理者がパートスタッフの「労働予定時間」を入力した段階で、システムが自動的に法定ルール(6時間超で45分、8時間超で60分)をチェックし、シフトに休憩時間を自動で組み込むことが可能です。これにより「そもそも休憩時間の付与が漏れる」という計画上のミスを未然に防ぐことができ、管理者は当日勤務時間が変動した際の休憩時間に配慮するだけで済むようになります。
【システムに関する補足】
休憩時間をどこで控除するかはシステムによって異なります。
- 勤怠システム側で休憩時間を控除
打刻データから休憩時間が自動で差し引かれ、「実労働時間」として給与システムに連携される。 - 給与システム側で控除
勤怠システムは打刻情報のみを渡し、休憩時間の按分・控除は給与計算システム側の設定で行う。
② 変則的な休憩形態への対応力
勤務の際の中抜けや分割休憩といった変則的な休憩形態へもシステムは対応することができます。休憩の開始・終了を打刻させることで、正確な休憩取得実績を把握し、サービス提供の合間の中抜け時間当も正確に集計・控除できます。休憩管理の自動化は、管理者・責任者が抱える「気づかぬうちに法違反をしてしまうかもしれない」という心理的な重荷からも解放してくれるのです。
4.勤怠システム導入で得られる具体的なメリット
ここでは短時間勤務の勤怠課題解決を超えて、システム導入で得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
4-1.システムで勤怠管理を行うことによる正確な勤務実態の把握
紙のタイムカードや出勤簿で避けられないのが、不正打刻や打刻忘れといったヒューマンエラーです。現場のスタッフが忙しさもあって打刻を忘れるケースもあります。こういったことに関しても、勤怠管理システムを導入すれば打刻の正確性を上げたり打ち忘れを改善することも可能です。
●不正を防止する多様な打刻方法
交通系ICカードを利用したり、顔認証やGPSなどスマートフォンを使って打刻を行うことができ代理打刻のリスクを排除することができます。
- 交通系ICカード
SuicaやPASMOなど職員本人が持っている交通系ICカードを使って打刻するものです。本人の物理的なカードがなければ打刻できないため一定の不正防止効果があります。 - 顔認証
打刻の際にタブレットやスマートフォンのカメラで顔認証を行うものです。事前に顔写真の登録が必要ですが本人の顔を打刻時の認証に使うため高い不正防止効果があります。事務所の入口にタブレットをおいてそこで顔認証することや、出先で直行・直帰をする場合はスマートフォンの顔認証で打刻することができます。 - GPS(位置情報打刻)
スマートフォンで打刻をする際にGPSによる位置情報を取得し許容する範囲内にいる場合に打刻ができるというものです。これにより、送迎業務などで直行直帰するパート職員に対しても、打刻した場所が事前に定めた勤務エリア(例:施設周辺、指定の利用者宅)の範囲内であるかを確認することができます。
4-2.配置基準チェックとシフト作成の効率化
通所介護施設にとって、サービス提供時間における人員配置基準の遵守は、介護報酬請求の前提となる絶対条件です。短時間勤務の職員が多数いて手作業でカウントしていると間違いが起こってしまうリスクも上がりますがシステム化することでシフトの作成の段階から正しい人員配置を行っていくことができます。またシフト作成時には資格が必要な職員がシフトに入っているかチェックも行います。さらに、シフトに入っている職員を変更した際も人数や資格を満たしているか随時チェックするため、人員配置基準を守ったシフトを策性することができます。
5.短時間勤務の課題解決に強い介護向けシステム
短時間勤務の集計や休憩時間の管理に特化してシステムを比較する場合、「集計の正確性」と「介護特有の機能」が鍵となります。ここでは、先に紹介したシステムの中から、通所介護施設の課題解決に強いシステムをご案内いたします。
| システム名 | 短時間勤務の集計精度 | 休憩時間の自動割当(付与)機能 |
| CAERU勤怠 介護 | 多様なシフトや1分単位の計算に完全対応。 | 自動割当が充実。勤務時間に基づき法定休憩時間を自動でシフトに割当。中抜け・分割休憩も正確に控除。 |
| カイポケ | 日々の勤務時間変動も正確に管理。介護記録アプリも兼ねており介護実績から勤務時間の取得も可能。 | 法定休憩時間を自動で割当・付与。 |
| ShiftMAX | エクセルベースのインターフェースで、短時間勤務のパターン設定も容易。 | 勤務時間に応じた休憩の割当に対応。 |
| ケアズコネクト | 勤怠管理だけでなく、記録や請求と連携して一元管理。 | 労働基準法に準拠した休憩の自動割当・控除に対応。 |
| MOT勤怠管理 | 顔認証など多様な打刻方法に対応し、短時間勤務の管理も正確。 | 労働時間に応じた休憩時間の自動割当・控除が可能。 |
| ToucheeZ QR勤怠 | QRコードやGPSなど、多様な打刻方法で直行直帰の短時間勤務も正確に管理。 | 打刻実績に基づき労働時間を計算・控除。 |
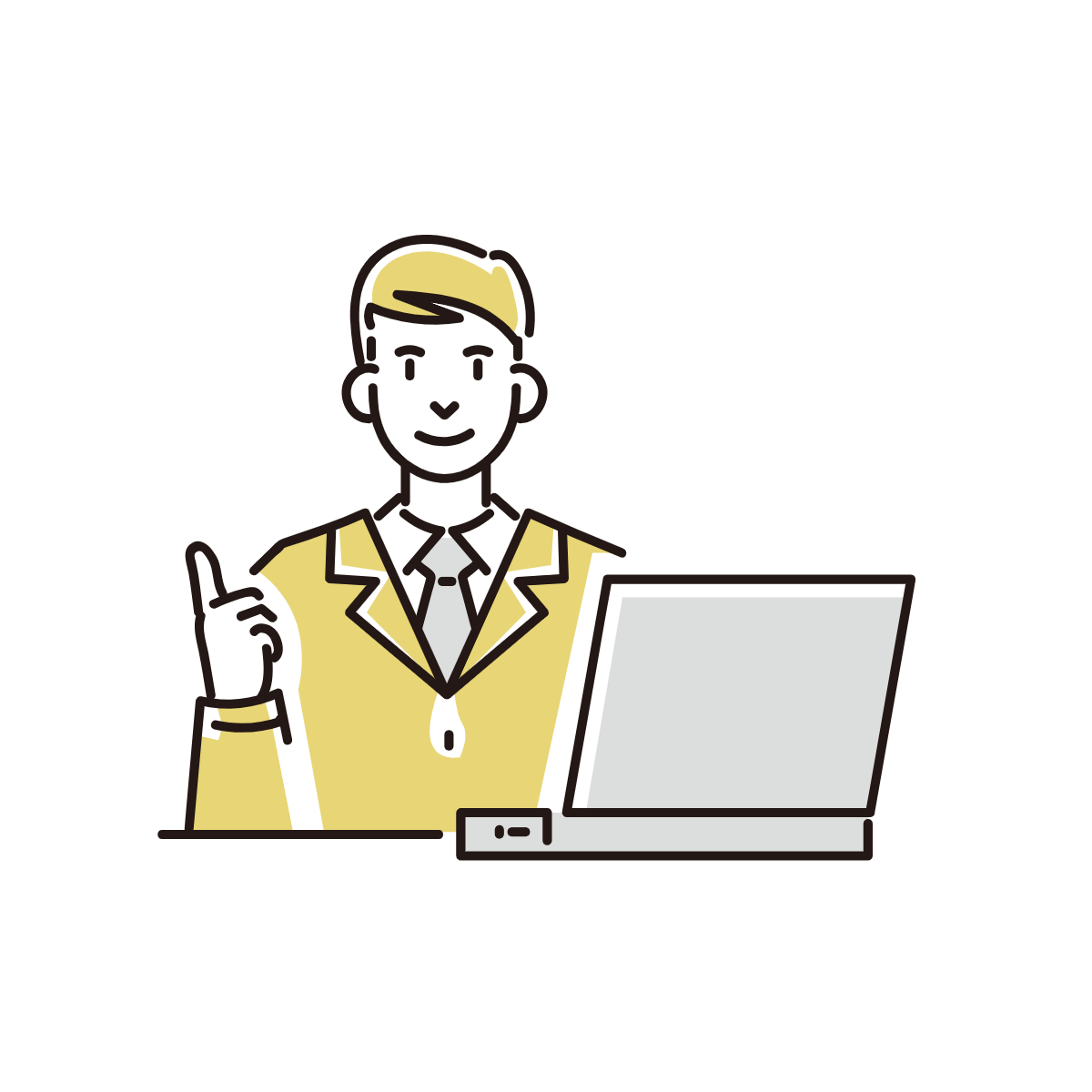
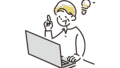
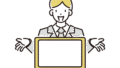
コメント