給与計算ソフトを導入せずに毎月の給与計算を行っている企業もまだまだいらっしゃるのではないでしょうか。手作業ならではの打ち間違えや修正に時間を取られ、毎月月初は給与担担当の負荷が高まることも多いかもしれません。この記事では給与計算ソフトを入れると解決できる課題や、ITに詳しくなくても給与計算ソフトをどうやって使っていけるか、新たにかかるコストに対して得られるメリットの説明方法など、給与計算ソフトを導入するための最初の社内提案に使える情報をまとめました。ぜひこの記事の内容を使って自社への給与計算ソフト導入のドアを開けてみてください。
1.給与計算ソフトとは
ここでは給与計算ソフトとはどんなものかを簡単にご案内しながら、どのようなソフトが中小企業に向いているかご案内いたします。
1-1.給与計算ソフトとは給与や控除を自動で計算してくれるもの
給与計算ソフトとは、社員の勤務日数や勤務時間を入力することで社員の給与や税金・社会保険料などを自動計算できるものです。具体的には毎月の給与明細に入ってくる、一人一人の基本給や残業代など各種手当を算出したり、所得税や健康保険・年金・雇用保険などの控除も算出します。なお賞与(ボーナス)や源泉徴収票の計算も可能です。
税率や保険料は法令で決まっているため給与計算ソフトに所得税や健康保険等の計算式が組み込まれています。そのためソフトを使えば所得税や各種保険料も間違いなく計算することができます。
1-2.中小企業には初期投資が小さいクラウド型がおすすめ
給与計算ソフトには、クラウド型とパッケージソフト型があります。
クラウド型もパッケージソフトももちろんどちらでも給与計算は行うことができます。大きな違いは料金体系にあり、クラウド型は毎月費用がかかる月額の料金体系で、対するパッケージ型は最初に購入して使用する買い切り型です。
代表的なソフトとしては、クラウド型では「freee」「マネーフォワード」「ジョブカン」等があり、パッケージソフトでは「弥生」「給料王」等があります。
クラウド型は基本的には社員数一人当たり●●●円という料金体系です。社員数が増えて長期間使用すると負担額も増えていきがちですが、毎月費用を払うクラウド型のため最新の税や保険料にシステムが対応してくれます。初期費用がかからなかったり、社員数もそこそこの規模でしたら月額費用もそこまで膨らまない利点があります。なおかつクラウド型なら最新の税や保険料が反映され、法令改正で税や保険料の料率を手動で変える手間がないため、中小企業にはクラウド型がおすすめと言えます。
なおパッケージ型については、最初に万円単位のソフト購入費がかかりますが、長期間利用するほどお得になります。但し税や保険料については改正されるごとに手動で設定変更するなどの対応が必要になります。
2.どんな課題が解決できるか
ここでは給与計算ソフトを導入するとどんな課題が解決するかご案内いたします。
2-1.給与計算の自動化
給与計算の自動化が、給与計算ソフト導入の一番のメリットと言えます。出勤日数や勤務時間、残業時間、各種休暇や欠勤あり・なしの情報が給与計算ソフトに入ると、あらかじめ社員ごとに設定してある基本給から残業手当などを支給額を自動で算出することができます。控除についても、算出された支給額から所得税や健康保険、年金、雇用保険、介護保険できます。
2-2.給与の自動振込も可能
社員全員分の給与計算が完了して手取り額が算出できたら、給与振込も簡単に行うことができます。
あらかじめ給与計算ソフトに社員の給与受取口座を登録しておけば、給与計算ソフトからワンクリックで銀行に振込金額(手取り金額)と受取口座のデータを銀行へ転送して、自動で社員の給与振込を行うこともできます。ただしこの給与の自動振込機能は、給与計算ソフトにより、社員の給与振込データを転送できる銀行が限られており、普段給与振込に使用している銀行が対応していない場合もあります。とても便利な機能ですが利用を検討する場合は、ソフトが対応している銀行を事前に確認することをおすすめします。
2-3.勤怠管理システムとの連携で二度打ちなし
給与計算ソフトに社員ごとの出勤日数や勤務時間、各種の休暇日数等の勤怠データを登録して給与や手当を割り出します。勤怠管理システムを使って社員の出勤・退勤の打刻や、休みの申請をしている場合は、勤怠のデータをそのまま勤怠管理システムから給与計算ソフトに連携することもできます。この連携を行うと、給与計算ソフトへ社員の勤務日数や残業時間を手打ちすることがなくなり、二度打ちの手間や打ち間違えを無くすことができます。
実際に連携する場合の手順としては、勤怠管理システム上で、月末にエラーの無いきれいな状態で月締め処理を行い、その後に全社員の勤怠データを給与計算ソフトへ取り込む流れとなります。
勤怠管理をタイムカードや出勤簿で行っている場合は、毎月出勤日数や残業時間、休暇日数を集計してから、手打ちで給与計算ソフトへ手作業で入力する必要があります。各段階で集計間違えや打ち込みミスがあり得る方法のため、アナログでの勤怠管理を行っている場合は、この機会にぜひ勤怠管理システムを導入して、勤怠も電子化してしまうことをおすすめいたします。勤怠の電子化と給与計算の電子化を同時に行えれば、人事労務の効率化を一気に図ることができます。該当する場合はぜひご検討ください。
⇒勤怠管理システムと給与計算の連携についてはこちらの記事「勤怠管理と給与計算のシステムを連携して手間もミスも削減!月次業務を便利に」で詳しくご案内しています。
2-4.WEB給与明細でペーパレス化
特にクラウド型の給与計算ソフトには、Web給与明細機能が多くの場合ついています。Web給与明細は、社員がWeb上で毎月の給与明細を確認できるようにするシステムで、この方法を採用すると紙の給与明細を廃止することもできます。
ちなみに実際にWeb給与明細を導入して紙の明細を廃止する場合は法令で社員の同意を取る必要があるとされています。
⇒Web給与明細の導入についてはこちらの記事「Web給与明細システム 導入の流れと代表的なシステムの紹介」で詳しくご案内しています。
Web給与明細を導入できれば、紙の管理の手間や費用も削減することができます。手渡しや拠点への発送の手間も無くすことができ、社員もいち早く明細をWeb上で確認することができます。
2-5.税や社会保障の法改正にも対応可能
所得税や各種の社会保険が制度の改正で税率や社会保険料率が変わった場合でも、特にクラウド型給与計算ソフトであれば、自動的にソフトがアップデートされ、改正以降は正しい税率や保険料率で給与計算を行うことができます。
パッケージ型の場合は、制度改正があった場合は自分で税率や保険料率を変更する必要があります。この点でクラウド型は自動で対応してくれるため、社会保険の仕組みにそこまで精通していない担当者の方でも安心して業務にあたれるのではないでしょうか。
3.ITに詳しくなくても利用できるか
ITに詳しくなくても給与計算ソフトは使えるのかについて気になる方もいらっしゃるかと思います。ここではどのような方法で給与計算ソフトをうまく使っていけるか対応方法をご案内いたします。
3-1.サポート体制の確認
給与業務には詳しいけれど、システムについては専門外という方も多くいらっしゃると思います。そのため給与計算システムを検討する際にはサポート体制をよくよくご確認いただくことをお勧めいたします。代表的なソフト会社のサポートは以下のようなものがあります。会社によって、ある、ないが異なります。
- ヘルプページ
どの給与計算ソフトにもあるのがこのヘルプページです。操作方法の説明からよくある質問まで、様々な情報が掲載されています。わかりやすい言葉で説明されているか、わからないことが調べやすそうか、文字だけでなく動画や画像で説明しているかなどの観点で、ヘルプページの充実を調べることもできます。 - 電話サポート
操作説明についてコールセンターを設けている給与計算ソフトの場合は電話による質問も可能です。電話サポートは行っていない給与計算ソフトもあるため、重要なサポート手段と考える場合は電話サポートの有り無しは必ず確認されることをおすすめします。 - 有人チャットサポート
有人チャットでサポートを受ける方法です。質問をする側も、回答する側も、チャットで質問と回答を行います。チャットボットと違い、人が回答に関わるため聞きたいことに対して割と正確に返ってくるのが特徴です。 - チャットボット
こちらは、質問する側が質問を選んだり入力したりして、機械が回答してくるチャットです。定番の割と初歩的な質問に対しては回答が用意されていることが多いですが、質問によっては的外れな回答が返ってくることもありますので少し注意が必要です。
3-2.画面の操作はわかりやそうか
給与計算ソフトの画面を事前に見てみることも、導入後になるべく迷わずに使っていく上では大切です。
給与計算ソフトの公式サイトを見ると、各機能を説明しているページで、給与計算ソフトの画面が出ていることがあります。クリックすると画面の動きをシミュレーションすることができる場合があるので、そういったところからこの給与計算ソフトはわかりやすそうか調べてみることができます。少し調査に時間はかかるかもしれませんが、画面を見るとどのような機能が搭載されているかもわかるため、ぜひ検討する給与計算ソフトの画面も見ていただくことをおすすめします。また、クラウド型給与計算ソフトの場合は無料で体験版を利用することもできることが多いので、実際に体験版を使って中を操作してみることもお勧めいたします。
4.メリット・デメリット
ここまでで給与計算ソフトの導入でどんな課題が解決できるか、ITに詳しくない場合でもうまく使っていく方法を整理しましたので、ここでは給与計算ソフトのメリットとデメリットをご案内いたします。
4-1.メリット
- 給与計算業務の手間の削減と正確さの向上
給与計算ソフトの一番のメリットは、やはり給与計算が自動化できるため手間が削減でき、なおかつ正確さが向上することです。今までは給与担当でないと複雑な税や社会保険の料率の仕組みがわからず、正確な業務ができているか判断がつかない問題もありました。この点でソフトが正確な税計算や社会保険料の計算をしてくれるので、給与業務に詳しい方に匹敵するような業務を自動で実現することができます。 - 業務の俗人化に歯止めがかかる
1つめのメリットにもつながりますが、税や社会保険の専門的な知識が要る給与業務の実務を給与計算ソフトが行うため、給与計算業務において熟練の給与担当の手数を減らすことができます。急病などで給与計算の担当が長期間休みになった場合でも、計算の実務はソフトが行うため給与計算業務を継続することも可能です。最後の確認はやはり給与や税をわかっている人が行う必要はあるかもしれませんが、給与計算ソフトを導入することで俗人化に一定の歯止めをかけることもできると言えます。 - 税や社会保険の制度改正に自動でシステムが対応できる
これはクラウド型が主になりますが、制度改正にシステムが自動対応するため、ある意味この面でも税や社会保険に熟知した担当でなくても、制度改正があっても業務を継続することができます。給与計算ソフトの特にクラウド型にはなりますが、この点でも属人化への対策となり継続的に安定して業務を継続していくことができます。
4-2.デメリット
- コストがかかる
一番のデメリットは「コストがかかる」ということかもしれません。クラウド型では毎月社員数に応じて利用料がかかり、パッケージ型では導入時に数万円のコストがかかります。これまで手作業を給与計算を行っている場合は、これまでは要らなかった新しい経費がかかることになり理解が得られず導入が進まない例もあるようです。こういった場合には、給与計算システムを導入すれば、例えば紙の給与明細を廃止しWebの給与明細に移行することでコスト削減できたり、サポートを使うとITに詳しくなくても導入しした給与計算ソフトをきちんと使って、効率化やミスを減らす提案もできるのではないでしょうか。そのような場合はぜひ提案をご検討ください。 - これ以外のデメリットは
これ以上のデメリットというと、うまく給与計算ソフトが使えればもうコスト以外のデメリットは無いといえるのではないでしょうか。速く正確に給与計算ができ、WEB給与明細で紙コストも削減でき、俗人化も緩和できる給与計算ソフトはぜひ導入したほうがいいでしょう。
5.サービスラインナップ
ここでは給与計算ソフトのサービスラインナップをご案内します。サービス名をクリックすると公式サイトへリンクします。
| サービス名 | 提供元 |
| freee人事労務 | フリー株式会社 |
| 給料王 | ソリマチ株式会社 |
| 弥生 | 弥生株式会社 |
| Smile Works | 株式会社スマイルワークス |
| One人事 | One人事株式会社 |
| 給与計算くん | 株式会社グッドウェーブ |
| ジョブカン | 株式会社DONUTS |
| マネーフォワード | 株式会社マネーフォワード |
| ジンジャー | jinjer株式会社 |
| ハーモス | 株式会社ビズリーチ |
| 奉行クラウド | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| CYBER XEED | アマノビジネスソリューションズ株式会社 |
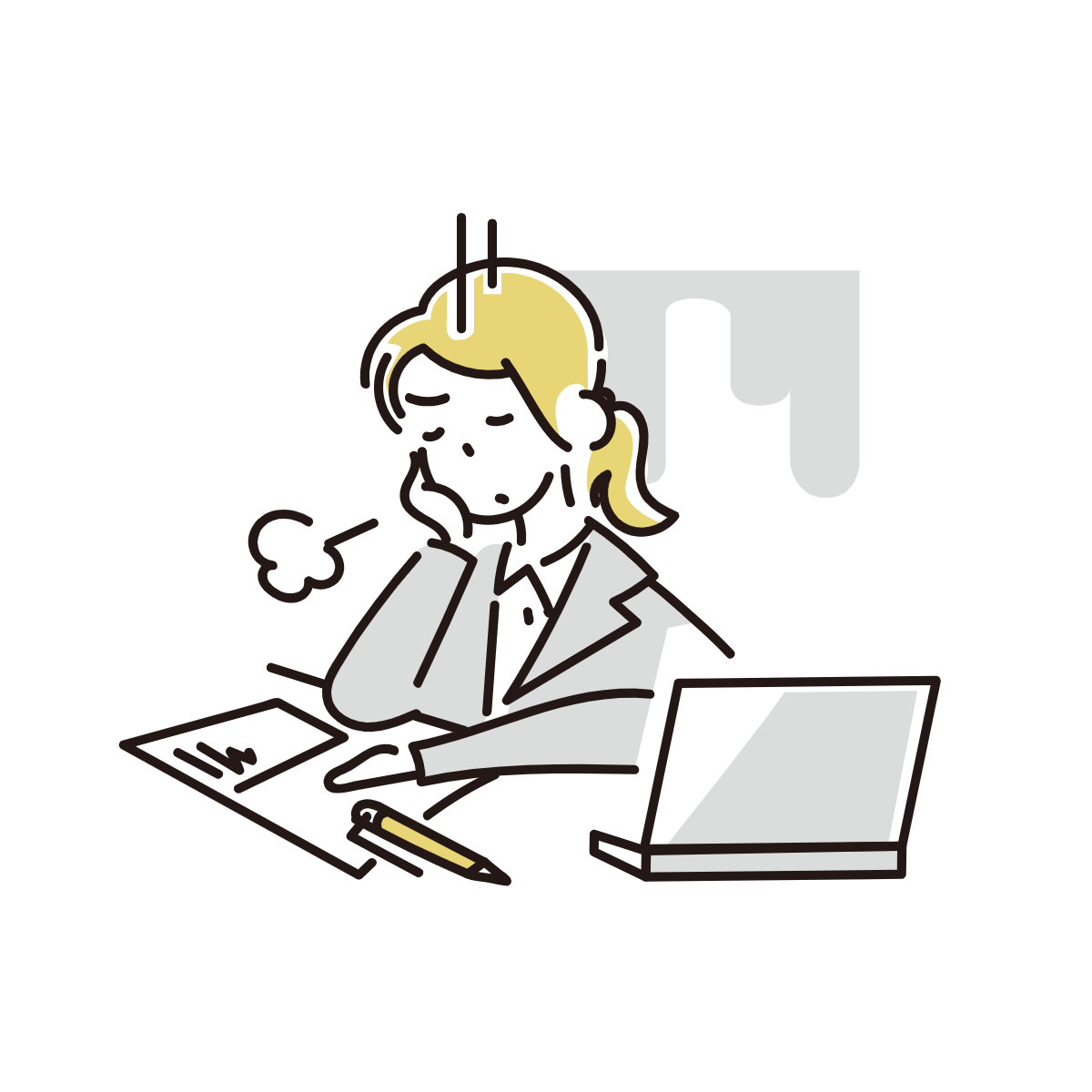

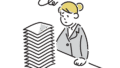
コメント