事務所への入室用の鍵やICカードの紛失を減らしたり、入退出の際のセキュリティを向上させたいとお考えの、中堅・中小企業の総務担当やシステム担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事ではそんな鍵の紛失やセキュリティの向上を検討されている担当者の方に向けて、従来の物理キーをスマートフォンに変えて利用できる入退室管理アプリ(別称:入退室管理とも言います)をご案内しています。入退室管理アプリとはどのようなものかから、用途や活用シーン、必要になる機器類、メリット・デメリットまで掲載していますので、ぜひ入退室管理アプリの選定に進んでみてください。
1.入退室管理アプリとは?
ここでは、入退室管理アプリとはどのようなものか、まず最初に知っていただきたいことをご案内いたします。
1-1.入退室管理アプリとは?その基本的な仕組み
入退室管理アプリとは、入退室の履歴管理や利用者ごとのアクセス権の付与などを一元的に行うシステムです。このシステムは、スマートロックや専用のICカードリーダーなどの機器と連携して入退室や解錠施錠の管理を行います。利用者は、スマートフォン、タブレット、ICカードなど、状況に応じて様々な方法で認証を行い、解錠・施錠を行います。
【基本的な仕組み】
- アプリで情報を管理する
管理者が専用アプリ(管理画面)上で、利用者の登録・削除、アクセス権限の設定、入退室履歴の確認などを行います。 - 利用者が解錠・施錠の認証や受付を行う
利用者は、以下のいずれかの方法で認証を行います。
【スマートフォン】
専用アプリをインストールし、スマートフォンに内蔵しているNFCやBluetooth、画面上で生成されるQRコードなどを使って認証します。
【タブレット】
入口に設置されたタブレットで顔認証やQRコード認証を行う。
【ICカード】
従来のICカードを専用リーダーにかざす。 - 機器が連動して解錠・施錠を行う
認証が成功すると、スマートロックが作動して扉が解錠されます。 - 入退室履歴が記録される
誰が、いつ、どこに入ったかという情報がリアルタイムで記録され、アプリ(管理画面)上で確認できます。
1-2.従来のICカードや物理キーとの違い
入退室管理アプリは、従来のICカードや通常の鍵(物理キー)と比較して管理の柔軟性とセキュリティ面でメリットを持っています。
【物理キーの特徴】
- 紛失リスクがある
鍵を紛失すると、合鍵の作成やシリンダーの交換といった手間とコストがかかります。 - 管理面のわずらわしさ
鍵の貸し借りや返却状況がアナログ管理になりがちで、そもそも物理的で小さな鍵なのでヒューマンエラーが発生しやすいものです。「鍵が無いけど、誰が持っているの?」という経験は誰しもにあるはずです。 - 履歴の不透明性
入退室履歴が記録されないため、セキュリティ面で脆弱性が残ります。物理キーの場合は紙のノートに入退室記録を書いているケースもあると思いますが、記入漏れの入退場は当然記録に残りません。
【ICカード・社員証】
- 発行・更新コスト
新入社員や退職者が出るたびに、カードの発行や回収、再発行のコストがかかります。また多めに在庫カードを持ってしっかりと管理する手間もかかります。 - 持ち忘れ・紛失リスク
ICカードを忘れたり、紛失したりすると、再発行の手続きが必要です。 - コロナウィルスなどの感染症対策リスク
非接触型が主流とはいえ、薄いICカードなので勢いで不特定多数が共有するリーダーに触れる機会があります。
【入退室管理アプリ】
- 紛失リスクの低減
スマートフォンは、物理キーやICカードに比べて比較的常に注意しつつ持ち歩くもののため、紛失に気づきやすく紛失リスクは低いとも言えます。またスマートフォンを紛失しても遠隔でロックすることも可能なため紛失時の安全対策も早期に講じることが可能です。 - 管理の効率化
アプリ上で利用者の登録や削除が簡単に行え、もちろん鍵(物理キーや専用ICカードなど)の受け渡しが不要になります。 - 履歴の自動記録
入退室の履歴が自動で確実に記録され、PCやスマートフォンでいつでも確認できるため、セキュリティ管理を強化することができます。 - 利便性
スマートフォンやICカードなど、複数の認証方法を選べるため、利用者の利便性を向上させることができます。
2.入退室管理アプリの主な用途と活用シーン
ここでは、入退室管理アプリの主な用途と活用シーンについてご案内いたします。
2-1.オフィスでの利用(社員や来訪者の入退場管理)
入退室管理アプリはオフィスでの社員の入退室管理に活用することもできます。
これまでは社員証に(別のICカードも重ねて利用している場合もありますが)入退室の機能を持たせていることがあります。これも、スマートフォン内に社員証を持たせることができ、そのままスマートフォンをオフィスの出入口でかざして入退場管理に利用することができますを行うことができます。またこの場合、物理的な社員証の発行や再発行の手間、コストも削減することができます。
また、入退室管理の記録を勤怠管理システムと連携させ、出退勤時間の自動記録を行うことも可能です。これにより勤怠管理システムやタイムカードへの打刻漏れも防止することができます。
さらには社員以外の来客受付にも入退室管理アプリは利用することができます。事前に来訪予定のお客様へQRコードをメールなどで送っておき、 来訪者が受付でそのQRコードをかざし来社受付することもできます。その際、社内の担当者へも自動で通知を送ることができ、受付業務を無人化しつつスムーズな対応を実現することができます。
2-2.学校・学習塾での利用(生徒の登下校管理と保護者への通知)
教育現場でも入退室管理アプリを活用して児童や生徒の登下校を管理することができます。児童や生徒が学校や塾に登校や下校した際に保護者のスマートフォンへ自動で通知が送ることも可能です。また出入口の施錠と連動させれば不審者の侵入防止を図りセキュリティを向上させることもできます。授業への出席管理の観点からは、登下校時間の記録を確認することで遅刻や早退の状況を正確に把握して指導に活用することもできます。
2-3.商業施設・イベント会場での利用(入場管理や混雑状況の把握)
入退室アプリは企業内の入退室管理だけに利用するのではなく、イベント会場であったり商業施設での入場管理で利用することも可能です。例えば入場用のQRコードを入場券代わりに発行して、入場口でQRコードをかざして入場を受付することもできます。比較的大人数でもスムーズな入場ができ混雑が緩和できることや、正確な入場数を把握することもできます。入退室管理アプリは基本的にクラウド環境で稼働しているため混雑状況もリアルタイム把握することができます。現在の入場数を基にした従業員の配置などの安全管理に活用することも可能です。
3.入退室管理アプリの運用で使われる機器類
ここでは入退室管理アプリの運用で使われる機器類についてご案内いたします。
3-1.スマートフォン(鍵)
スマートフォンは、入退室管理システムにおいて利用者の鍵として使われるだけでなく、管理者の入退室管理システムの運用ツールとしても利用することができます。
スマートフォンを入退場時の鍵として利用する場合は、専用のアプリをインストールしたり、スマートフォン内蔵のICカード機能(NFC)を利用したり、内蔵のBluetoothを使って施錠や解錠ができます。Bluetoothを使った場合は、ドアに近づくだけでスマートフォンをかざことなく解錠や施錠を行うことができます。余談ですが最近のマンションのエントランスでも利用されています。
また、スマートフォンは利用者の鍵として利用するだけでなく管理者の入退室管理システムの運用ツールとしても利用できます。スマートフォンアプリ上で管理者は従業員の入社や退職に伴う利用者情報の登録や削除、入場可能エリアへ権限設定、入退室履歴なども確認できます。入退室管理アプリの運用業務も場所を選ばずにスマートフォン上で行うことができます。
3-2.専用リーダー(鍵穴)
入退室管理アプリを使った解錠・施錠の運用には、スマートフォンなどを鍵として利用しますが、鍵穴にあたるのがこの専用リーダーになります。
専用リーダーは、建物の入口や各部屋の入口に設置されており、既に警備会社の警備開始や解除の専用リーダーを見た方もいらっしゃると思いますが、入退室管理アプリも見た目には似たものとなります。
この入退室管理アプリは警備会社のリーダーとは目的が違うため、日々の入退室管理が楽にできるよう、複数の認証方法に対応しています。
- QRコードリーダー
スマートフォンアプリに表示されたQRコードを読み取るためのQRコードリーダーのことです。アプリ内でQRコードを保持しておくこともできるためスマートフォンの通信環境に左右されずに素早く認証することができることも特徴です。 - NFC/FeliCaリーダー
スマートフォンのNFC機能をかざして認証します。また従来の交通系ICカード(FeliCa)を鍵として使う際にもNFC/FeliCaリーダーを鍵穴として利用します。 - Bluetoothリーダー
専用リーダーから発しているBluetoothの通信範囲内に事前設定されたスマートフォンが入ると自動的に認証を行うことができます。スマートフォンがポケットやバッグに入ったままでも解錠できるため、両手がふさがっている時でも便利に解錠や施錠を行うことができます。
3-3.スマートロック(鍵穴の心臓部)
このスマートロックは、専用リーダーから解錠や施錠の認証信号を受けて、物理的な鍵を使わずに扉の施錠・解錠を行うデバイスです。既存の鍵穴に箱のような装置を取り付ける後付けタイプや、工事や取り換えを行い扉の鍵穴部分に埋め込んで利用するタイプもあります。
このスマートロックが入退室管理アプリの心臓部とも言え、専用リーダーにスマートフォンをかざした時の解錠はもちろんのこと、管理者のアプリ操作による遠隔での解錠・施錠も可能にします。鍵の閉め忘れなどのようなことが起きてもスマートロックによって施錠できるため、セキュリティも向上させることができます。またもちろんのこと入退室アプリ側で設定した利用者ごとの権限管理にしたがってスマートロックが権限のある利用者だけ解錠・施錠するように動作しています。
3-4.タブレット端末(受付としての利用)
受付にタブレット端末を設置することで、お客様向けの来客受付システムとして利用することもできます。この機能だけを既に導入している企業もあるかもしれませんが、 来訪者がタブレットで自分の名前を入力して訪問先を選択すると、担当者へ自動で通知が送られます。それ以外にも事前にQRコードを発行しておけば、それをかざすだけで受付が完了するなど来訪者対応をタブレットでスムーズに行うことができます。
このほかにも、タブレットを使い顔認証を行うことで解錠まで行うタイプもあります。事前に顔写真の登録などが必要となりますがセキュリティを重視する場所では顔認証を利用して受付を運用することも可能です。
4.入退室管理アプリのメリット・デメリット
ここでは入退室管理アプリのメリット・デメリットについてご案内いたします。
4-1.【メリット】セキュリティの向上
入退室管理アプリを運用することのメリットとしては、まずどの場所に、誰が、いつ入ったかをすべて記録できることが挙げられます。日々、入退室をスマートフォンなどをかざして行っていくことで、記録は自動で記録し続けられます。何らかの出入りについて確認する事態が起こった際にも、いち早く入退室記録を入手することができます。物理キーでは不可能だった正確な入退室記録が入退室管理アプリを運用することで生成可能となります。
厳格なアクセス権限管理: 従業員の役職や部署、時間帯などに応じて、特定のエリアへのアクセス権を細かく設定できます。例えば、夜間や休日は特定の人しか入室できないようにするなど、柔軟かつ厳格なセキュリティ体制を構築できます。
紛失時のリスク低減: スマートフォンを紛失した場合でも、遠隔でアクセス権を無効化できるため、鍵の悪用リスクを最小限に抑えられます。物理キーやICカードの紛失のように、鍵交換や再発行といった手間やコストもかかりません。
4-2.【メリット】管理業務の効率化と利用者の利便性向上を図れる
入退室管理アプリのメリットは他にもあり、鍵の受け渡しが不要になることも大きいポイントです。従業員が増減してもアプリ上でアクセス権を付与・削除するだけで済むほか、物理キーやカードキーの貸与や回収、スペアキーの管理、キー類の棚卸しといった煩雑な業務を不要にすることができます。またキー類の紛失事故の防止にもつなげることができます。
他にも利用者の利便性向上の面では、常に持ち歩くスマートフォンが鍵になるため、鍵やカードを別に持つ必要がなくなり鍵の持ち忘れや紛失事故を防ぐこともできます。
4-3.【デメリット】スマートフォンの依存リスク
これまでスマートフォンのQRコードやNFC、bluetoothを鍵替わりにして解錠や施錠する方法をご案内してきました。スマートフォンは使い慣れていて便利な反面、バッテリーが切れると解錠ができなくなることがありどうしても解錠や施錠できなくなるリスクは残ってしまいます。もちろんICカードや暗証番号などの予備の認証方法を準備しておくことが重要です。スマートフォンも機種によってはバッテリーが切れてしまってもNFC(スマートフォン内蔵型のICカード機能)を予備電源で利用することができる機種もありますが、スマートフォン自体の紛失や故障もあり得るので、ICカードや暗証番号などの代替となる認証手段を用意しておく必要はあります。
4-4.【デメリット】ネットワーク環境への依存
入退室管理アプリの運用は、ネットワーク環境が稼働してこそ正常に行うことができるため、LANやインターネットが不安定になった場合は、認証に時間がかかったり認証できない場合もあります。ネットワークが不通になった場合には緊急解錠用の物理鍵があるかなど導入前には確認しておくことをおすすめいたします。
5.代表的な入退室管理アプリのご案内
ここでは代表的な入退室管理アプリのご案内いたします。
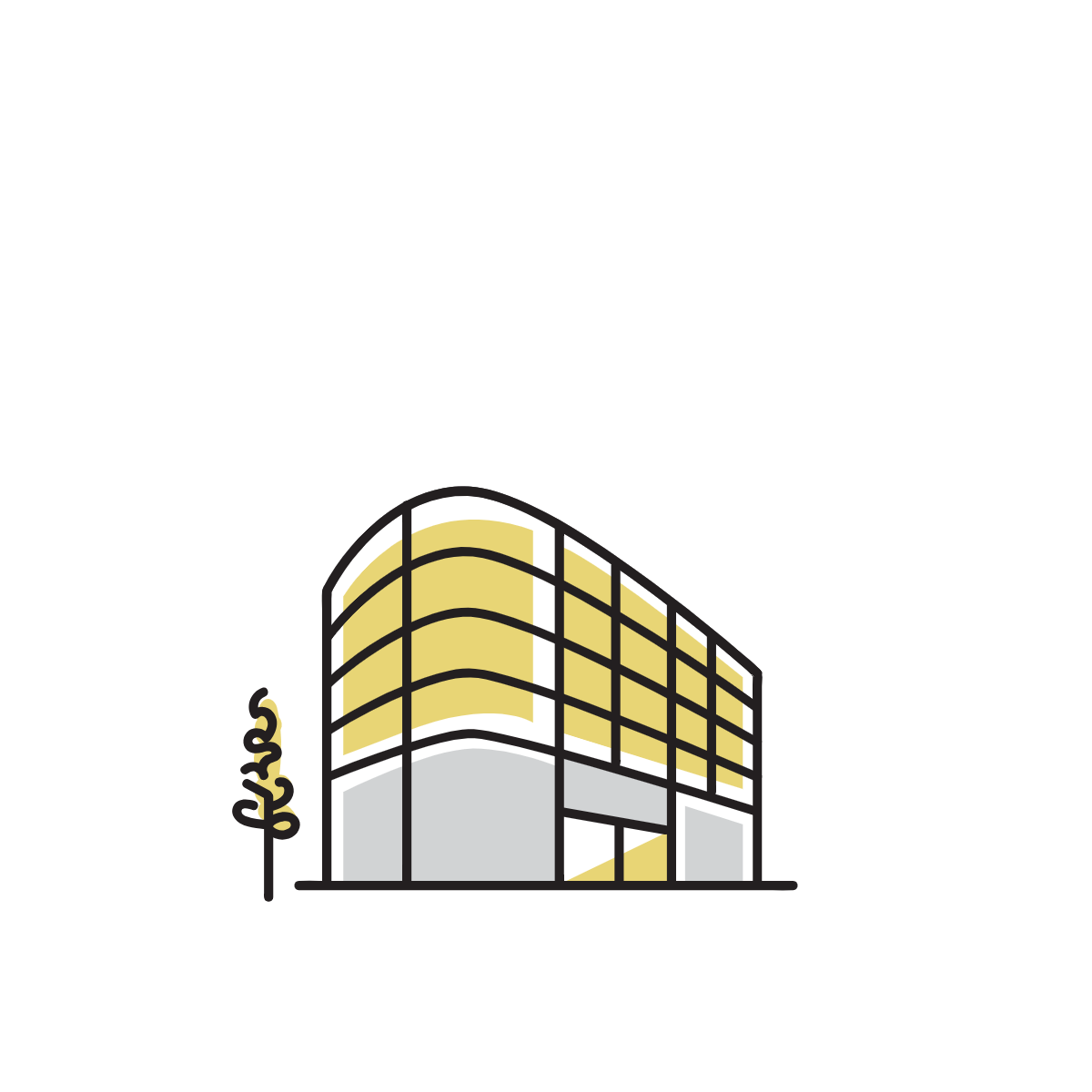
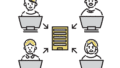

コメント