従業員サーベイの実施や利用するツールについて検討し始めた中堅企業や中小企業の総務・人事担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方のためにこの記事では従業員サーベイとはどのようなものかや、従業員満足度調査(ES調査)との違い、調査項目や質問例、実施の流れなどをご案内いたします。ぜひこの記事を読んで従業員サーベイの流れを把握して具体的なシステムの選定に進んでみてください。
1.従業員サーベイとは?
ここでは従業員サーベイとはどのようなものか、まず最初に知っていただきたいことをご案内いたします。
1-1.従業員サーベイとは何か?
従業員サーベイとは、組織に所属する従業員の意識や意見を定期的に調査する社内の活動のことです。会社の経営方針や職場環境、人間関係、個人の成長機会など、様々な項目をアンケート形式で従業員から収集します。これにより、働くうえで従業員が何に満足し、何に課題を感じているのかを可視化することができます。意見の収集だけでなく得られたデータを分析して組織課題の解決や改善策に役立てることもこの活動の重要な目的です。
かつては従業員満足度調査(ES調査)という呼ばれ方で従業員向けの調査を行っていること一般的でした。近年では、単に従業員の満足度を測るだけでなく、「従業員エンゲージメント」という概念が新たに注目されています。エンゲージメントとは、マーケティングなどでよく使われだしている言葉ですが、従業員にあてはめると、会社の目標やビジョンに共感し、自発的に貢献したいと深く思っている状態かを指します。従業員サーベイは、このエンゲージメントの状態を把握して向上させるためのツールとして位置づけられています。
1-2.従業員サーベイを実施する目的
従業員サーベイを実施する目的は多岐にわたりますが、主に以下の3つが挙げられます。
第一に、組織の課題を明確にすることです。経営層や管理職が認識している課題と、現場の従業員が感じている課題にはギャップがあることが少なくありません。サーベイによって、社内の隠れた不満や潜在的な問題を洗い出し、具体的な改善策を立てることができます。例えば、「給与や評価制度に納得感がない」「上司とのコミュニケーションが不足している」「業務量が多すぎる」といった声が可視化されれば、具体的な対策を講じることが可能になります。
第二に、従業員エンゲージメントを向上させることです。エンゲージメントが高い組織は、従業員のモチベーションが高く、生産性や創造性が向上すると言われています。サーベイを通じて、従業員が会社に求めることや、貢献意欲を高める要因を把握できます。その結果に基づき、従業員が「この会社で働き続けたい」と思えるような職場環境や制度を整えることができます。
そして第三に、離職率を低下させることです。従業員が抱える不満や不安を放置すると、最終的に離職につながります。サーベイを定期的に行うことで、離職の兆候を早期に察知し、先回りして対策を打つことができます。例えば、「キャリアパスが見えない」という声が多ければ、面談の機会を増やしたり、研修制度を充実させたりするなど、離職を防ぐための具体的なアクションに繋がります。これらの目的を達成することで、組織はより強固なものになります。
1-3.従業員サーベイが今、重要とされる理由
従業員サーベイは年を追うごとに重要性が高まっているとも言えますが、その背景には働き方の多様化や人材の流動化といった企業をとりまく変化があります。終身雇用やそこまでいかないまでも長期間にわたる勤続が当たり前ではなくなった現代は、企業は従業員に「この会社で働き続けたい」と思ってもらう努力を継続することも、優秀な人材を確保し続けることにつながっています。
またテレワークの普及で対面でのコミュニケーションが減少し、外からわかるような従業員の心理状態であったりコンディションや考えを把握することが以前よりも管理職にとっては難しくなっています。このような状況下で、従業員サーベイは、物理的に離れていても従業員の心理状態や組織へのエンゲージメントを把握するために利用できる貴重な手段となっています。従業員のパフォーマンスを最大限に引き出すためにも、従業員サーベイを利用して組織全体の課題だけでなく、部署ごと、チームごとの課題を特定することできめ細やかな改善を行うことも可能です。
2.従業員サーベイと従業員満足度調査(ES)の違い
ここでは従業員サーベイと従業員満足度調査(ES)の違いについてご案内いたします。
2-1.従業員満足度調査(ES)の視点
従業員満足度調査(いわゆる「ES」でEmployee Satisfaction)は、文字通り従業員が自身の仕事や職場に対してどれだけ満足しているかを測る調査です。給与、職場の人間関係、福利厚生、会社の制度など、主に外部から社員へ与えられることについての満足度を評価するものです。
このES調査の主な目的としては、従業員の満足を数値化し、不満の原因を特定することにあります。例えば「給与水準は適切か?」「休暇は取得しやすいか?」といった質問を通して従業員が会社に「何を与えられているか」を測ります。このES調査では満足度が高い状態は、従業員がその会社にとどまる理由の一つになり、離職率の低下に寄与すると考えられてきました。
しかしES調査には限界もあり、高い満足度を示している従業員が必ずしも会社への貢献意欲が高いとは限らないためです。例えばですが、個人の主観として「給与は良いし、残業も少ないから満足している」と言っても、必ずしも会社から業務上の良い評価を受けていない場合もあります。その逆もあると言えます。既存のES調査では組織の成長を促すような、自発的な行動や改善提案を行っているかなどを測ることができないため、近年ではES調査に代わり、より能動的な概念である「エンゲージメント」に注目が集まっています。
2-2.従業員(エンゲージメント)サーベイの視点
従業員(エンゲージメント)サーベイは、従業員が会社や仕事に対してどれだけ「熱意」だったり「貢献意欲」を持っているかを測るものです。ESのような単なる待遇への満足だけでなく、会社のビジョンや目標への共感、自分の仕事に対するやりがい、社会的意義、会社への信頼度などを重視します。
エンゲージメントサーベイの質問は、ES調査よりも内面的な要素に踏み込みます。例えば、「あなたは会社のビジョンに共感していますか?」「あなたの仕事は社会に貢献していると感じますか?」といった、従業員自身の内発的な動機や感情を問うものが中心となります。
企業理念や事業内容にビジョンが色濃く反映されていたり、社会貢献性が高い事業を行っている場合などは、比較的回答に取り組みやすいかもしれませんが、エンゲージメントが高い従業員は、会社の成功を自分の成功と捉えたり、困難な課題にも積極的に取り組んだり、周囲のメンバーと協力して仕事を取り組んだりする傾向があります。また、エンゲージメントが高い社員は離職リスクが低いだけでなく、生産性や創造性が高いことも多くの調査で示されています。このため、エンゲージメントサーベイは、単に不満を解消するだけでなく、組織全体のパフォーマンスを向上させるための計測ツールとしても位置づけられています。
3.従業員サーベイの調査項目と質問例
ここでは3.従業員サーベイの調査項目と質問例についてご案内いたします。
3-1.組織全体に関する項目
この組織全体に関する項目では、従業員が会社全体のビジョンや戦略をどれだけ理解し、共感しているかを測ります。会社の方向性や文化に対する認識を把握することで、経営層と現場の間のギャップを明らかにできます。
●質問例
・あなたは会社の経営方針やビジョンに共感していますか?
・会社の企業文化や価値観は、あなたの仕事に良い影響を与えていますか?
・会社は社会貢献や倫理的責任を果たしていると思いますか?
・経営層からの情報共有は十分だと感じますか?
これらの質問により、従業員が会社の経営方針などの「大きな絵」をどのように捉えているかがわかります。もし共感度が低い場合は、ビジョンの浸透施策や経営層からのメッセージ発信を強化するのも一つの改善案になります。
3-2.職場環境に関する項目
この職場環境に関する項目は、日々の業務における具体的な環境や人間関係、評価に対する従業員の感覚などを調査します。比較的従業員のモチベーションや生産性に直接的な影響を与えやすいものが調査対象となっています。
●質問例
・上司はあなたの意見を尊重し、建設的なフィードバックをくれますか?
・チームメンバーとの人間関係は良好だと思いますか?
・あなたの成果は正当に評価され、報酬に反映されていると感じますか?
・業務量は適切であり、ワークライフバランスを保てていますか?
これらの質問から、個々の従業員が直面している課題や、部署・チームごとなど比較的細かい粒度で問題が見えてきます。例えば、特定の部署で人間関係のスコアが低い場合、その部署でマネジメントなのか、構成人員なのかに何かの問題がある可能性が示唆されます。
3-3.個人の成長に関する項目
この個人の成長に関する項目は、従業員が自身のキャリアやスキル開発についてどのように考えているかを把握する項目です。「この会社で成長できる」という実感は、エンゲージメントを高める重要な要因とされています。
●質問例
・現在の仕事にやりがいを感じていますか?
・会社はあなたのスキルアップやキャリア形成を支援してくれますか?
・新しいスキルを学ぶ機会は十分に与えられていますか?
・部署異動や昇進など、キャリアパスは明確だと感じますか?
この項目で得られたデータは、人材育成プランやキャリア支援制度を見直す際に役立ちます。もし成長機会のスコアが低い場合、研修制度の拡充や、上司との定期的なキャリア面談の導入などを検討するきっかけにすることもできます。
4.従業員サーベイ実施の流れと注意点
ここでは従業員サーベイ実施の流れと注意点についてご案内いたします。
4-1.実施前の準備
サーベイを始める前に、まず自社における目的を明確にすることが重要です。「何のために従業員サーベイを行うのか?」という問いへの答えが、質問項目や分析方法、その後の改善アクションを決定づけるとも言えます。例えば、「離職率の改善」が目的なら、キャリアパスや評価制度に関する質問に重点を置くことをおすすすめします。
また従業員への周知と説明も丁寧に行うことが大切です。忙しいとついただのアンケート程度に思われてしまい適当な回答につながってしまうこともあり得ます。サーベイの目的、匿名性も確保されること、結果の活用方法などを従業員へ事前に説明して、従業員の協力を得ると回答率や回答の質を高めることができます。
4-2.調査の実施
従業員サーベイを実施する際は、利用するシステムやツールの選定が重要です。回答しやすい画面であったり、社員が親しみを持てるデザインであるか、データの分析機能は充実しているか、匿名性が確保されているかなどの確認が重要です。
回答期間の設定も検討事項ですが、従業員が無理なく答えられるように期間を設定することも大切です。また回答率を上げるためにも、回答状況を部署ごとに共有したり、リマインダーを送信したりするのも一案です。
4-3.分析と改善アクションの策定
従業員サーベイの結果が揃ったら分析を行います。全体の結果だけでなく、部署別、役職別、勤続年数別など、さまざまな切り口でデータを集計し、比較して分析することで、組織のどこに課題があるのかを深く掘り下げることができます。また分析結果に基づき具体的な改善アクションの策定も行います。社内の課題は道筋を付けたり経営陣の了解を取ったりするなど、解決に向けての行動は体力がいるものです。そのためすべての課題を一度に解決しようとせず、優先順位をつけながら取り組んでいくことをおすすめいたします。
4-4.フィードバックと結果の共有
従業員サーベイの結果を従業員にフィードバックすることは、信頼関係を築く上で不可欠と言えます。「結果が出たけど、その後どうなったか分からない」という状態は、従業員の不信感につながりがちです。ポジティブな結果はもちろんのこと、改善すべき課題についても共有を進めることをおすすめします。
策定した改善アクションについても、従業員に分かりやすく伝えることが重要です。例えば、調査が終わった一定期間後の何かの機会についでで今後改善していくことや進捗状況などを共有するだけでも意義があるのではないでしょうか。フィードバックを行うことで従業員の会社に対する信頼感も上がっていきます。
5.従業員サーベイツールのご案内
ここでは従業員サーベイツールをご案内いたします。
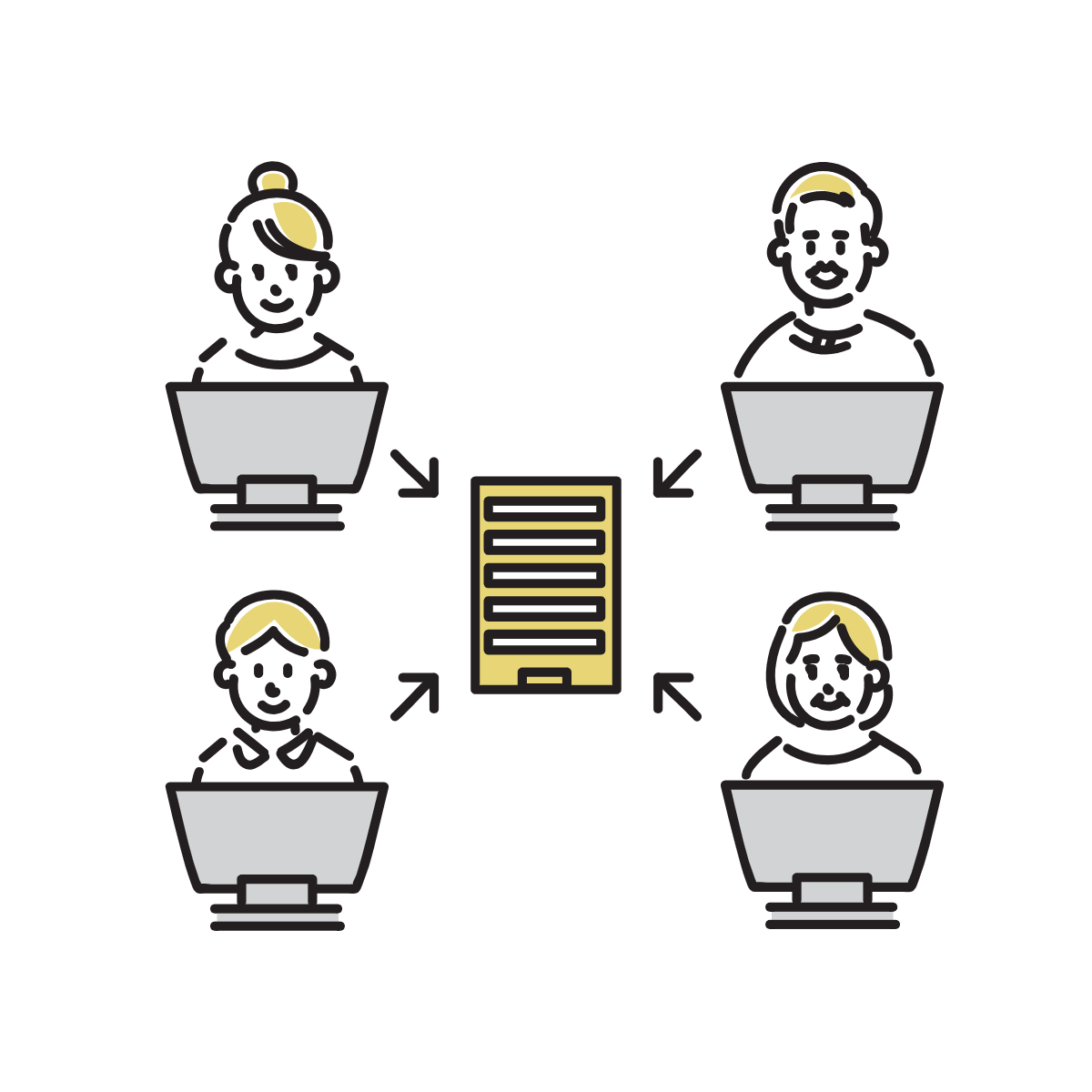

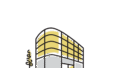
コメント