タイムカードや出勤簿を使っている企業も、勤怠管理システムを導入している企業も、ICカードでの打刻を導入すると労務管理や打刻の手間が削減できます。タイムカードや出勤簿を使っている場合は勤怠管理システムを導入する必要はありますが、ICカードリーダーは比較的安価に入手でき、社員の勤務時間も自動で取り込むことができます。本記事では労務管理の手間を削減したい企業に向けてICカードを使った打刻のメリット・デメリットや導入までの大まかな流れを解説します。ぜひこの記事を読んで自社でICカード打刻の導入が可能か環境を調査して、可能ならぜひ社内に導入してみてください。
1.ICカードを使った打刻とは?
ICカードを使った打刻とは、交通系ICカード等をカードリーダーにかざし社員が出勤や退勤の打刻をすることです。ICカードをかざすだけで誰が何時何分に出勤・退勤した情報が自動で勤怠システムへ取り込むことができます。かざす操作は、改札でICカードをかざすのと同じようにすればよく、誰でも簡単に日々の勤務時間の登録が可能です。
実際に運用するには、ICカードに対応した勤怠管理システムが必要です。その他にも、ICカードリーダーを用意したり、システムの設定をしたり、社員のICカードを登録したりと、ある程度の作業が発生します。
ここではメリット・デメリットや、どんな企業がICカード打刻を有効に使えるか、導入の流れもご紹介します。さらにはICカード以外の打刻の方法もご紹介しますので、参考にしてください。
1-1.低コストに導入する方法もある
ICカードを使った打刻は、(対応する勤怠管理システムが入ってる前提ですが)ICカードリーダーと交通系ICカードがあれば、ほぼ利用可能です。
ICカードリーダーは、後ほど詳しくご説明しますが、安いものでしたら1台数千円で購入でき、ICカードは社員が持っているもを使えば経費をかけずに利用可能です。(あとはカードリーダーを接続するパソコンは必要)
このよう比較的低コストに導入する方法もあります。
1-2.利用できるICカードの種類
勤怠の打刻では、以下の2種類のICカードが利用できます。
勤怠管理システムにより(1)と(2)の両方に対応する場合や、どちらかに対応する場合があります。
(1)交通系ICカードやnanacoやWAONといった電子マネー
・交通系ICカード(Suica、PASMO、ICOCA、TOICAなど)
・nanaco
・WAON
⇒『FeliCa(フェリカ)』規格のICカードと言われています。
※スマホやスマートウォッチに入れて使うモバイルSuicaやモバイルPASMOは対応できない勤怠システムもあります。
(2)ICカード型の社員証
ICカード型の社員証を使っている企業では(勤怠システムが対応していれば)社員証をリーダーにかざして打刻に利用可能です。
⇒『MIFARE(マイフェア)』規格のICカードと言われています。
2.ICカード打刻に必要な機器
日々の打刻でICカードを使うには読み取り機器が必要で、ここではその機器についてご案内します。
2-1.ICカードリーダーをPCにつないで使う
これが一番機器代が安く済む方法で、ICカードリーダーはアマゾンや電気店で市販されており、こちらをUSBでPCと接続して打刻に使用します。価格も1台数千円で売られており安価に購入できます。打刻専用の小型PCを1台用意して事務所の入り口などに起動したまま置いておくと早朝でも深夜でも便利に使えます。
2-2.ICカード打刻専用機を使う
ICカード打刻専用機というのは、ICカード打刻に特化した小型の打刻専用端末です。この打刻専用機にICカードをかざして打刻を行います。あまりイメージがわかないかもしれませんが、例えると昔のタイムカード打刻機を小型化してICカードの読み取り機能を付けたようなもの、と言ったらわかりやすいかもしれません。
2-3.ICカードリーダー内蔵のタブレットを使う
ICカードリーダーを内蔵したタブレットも市販されています。リーダーがタブレットに内蔵されているため簡単にすぐ利用できます。Wi-FiモデルのほかLTEモデルもありますので、社内Wi-Fiが無い場合はLTEモデルを選ぶとスムーズです。
3.メリット・デメリット
ここではメリットとデメリットをご案内します。
3-1.メリット
- 打刻操作が簡単で速い
打刻操作は社員がICカードをリーダーへかざすだけなので、誰もが簡単かつスピーディーに打刻をすることができます。紙のタイムカードで時々発生する、他人のタイムカードを間違って打刻してしまった・・・ということもなくせます。 - 導入コストを抑えらえる
ICカードリーダーは安いものであれば1台あたり数千円で購入可能です。また例えば社員の交通系ICカードを利用すればカードにコストをかけずに運用可能です。 - 打刻の時間が自動で勤怠システムに取り込まれる
ICカードリーダーは勤怠管理システムと接続して使いますので、社員の出退勤の時間を自動で取り込むことが可能です。紙のタイムカードを使っていた場合は、日毎の勤務時間の手計算および入力が自動化されますので、労務管理担当者の手間も削減することが可能です。 - 不正打刻を防ぐ効果がある
ICカードには1枚1枚に異なる番号が付与されています。このICカード番号をあらかじめ勤怠管理システムへ利用する社員の氏名とともに登録して運用します。こうすることで本人のカードをかざした場合にのみ、その本人が出退勤したことが記録でき、不正打刻を防ぐ効果があります。ただ本人のカードを他人に渡して代わりに打刻してもらう、ということは可能なため、完全に不正打刻を防げるわけではありません。ちなみに完全を期したい場合はタブレットで顔認証がおすすめです。 - ペーパレス化でコスト削減や社員の紙管理業務を無くせる
タイムカードや出勤簿といった紙で勤怠管理をしていた場合は、紙の購入費用を無くせます。また、過去のタイムカードや出勤簿を保管するなど紙の管理業務も無くすことが可能です。
3-2.デメリット
- ICカードを忘れると打刻ができない
あたりまえですが、社員がICカードを忘れるとその日の打刻はできなくなってしまいます。このような場合は、勤怠管理システムに出勤時間・退勤時間を手動入力するなどのフローを用意しておく必要があります。 - ICカードの紛失時には、新しいカード番号を勤怠システムへ再登録する必要がある
ICカードを紛失した際に、新しいカードを再発行した場合はICカードの番号が変わっている場合があります。場合により新しいカードを再発行しても、紛失時と同じICカード番号で再発行される場合もあるようで、ともかくカードを再発行した場合は、カードを再登録する流れにしておくと確実です。 - 直行・直帰やテレワークでは使えない
ICカードリーダーが必須のため、リーダーが設置されていない場所で勤務する場合は、ICカード打刻はできなくなってしまいます。そのため、直行・直帰やテレワークの際は、別の打刻方法を決めておく必要があります。
4.ICカードでの打刻が適した企業・職場
4-1.拠点が多すぎない企業
拠点が多すぎず、かつ従業員数もある程度以上(例えば20名以上)の規模の場合はお勧めできます。拠点が多い会社だと各拠点にICカードリーダーを購入・配布するコストが増えたり、故障時にも復旧に時間がかかることがあります。(リーダーはPCにつないで使用するため、打刻専用のPCを利用する場合はそのコストも多拠点だとかさみます。)また、ある程度社員数がいることで、出退勤時間を自動で勤怠管理システムへ取り込むメリットも活きてきます。
4-2.PCで業務を行わない職場
基本的にPCが1台あればICカードでの打刻は可能です。そのため業務でPCを使わない職場なら打刻用にPCかタブレットを1台だけ用意するだけで、打刻が可能です。
ICカードは短時間で打刻ができるため人数が多く主業務にPCを使わない職場(例えば飲食、小売、工場、スーパーマーケット等)では手軽に活用できるかもしれません。
4-3.交通系ICカードを使った電車通勤やバス通勤が多い職場
通勤で電車やバスを使う方が多い職場は交通系ICカードの所持率も高いため、ICカードでの打刻に適しています。都市部から近郊エリアの方が電車やバスの利用は多く、これらのエリアではICカードで打刻に対応できる社員も多いと言えます。
4-4.アルバイト比率の高い職場
アルバイトの比率が多い職場でもICカードでの打刻が適しているとも言えます。出勤や退勤の人数が多くても、スムーズに打刻ができるため速やかに業務の準備や退場に移ることが可能です。なおスマホに入れたモバイルSuicaやモバイルPASMOは利用できない勤怠管理システムが多いので注意が必要です。
5.ICカード打刻 導入の流れ
- 現在利用している勤怠管理システムがICカード打刻に対応しているか確認する
- ICカードリーダーを購入し、勤怠管理システムと接続してみる
最初は1台だけ購入して実際に打刻がうまくいくかテストすることをお勧めします。
打刻専用のPCを用意すると、夜遅い時間に帰る社員でもスムーズに打刻することができます。 - 問題なければ必要な数のカードリーダーを購入し、社員のICカード番号を勤怠管理システムへ登録する
- あとは社内にICカードリーダーでの打刻開始日を周知して利用開始する
この時、混乱防止のため、ICカードを忘れた場合や出張中はどう打刻を打つかなど、運用ルールをマニュアル化しておくことをおすすめします。
6.ICカード以外でおすすめの勤怠管理方法とは?
ICカード以外にも、最近は様々な機器で打刻ができるようになっています。ここでは一例をご紹介します。ICカード以外にも打刻の選択肢がありますので、必要でしたら併せて検討してみてください。
(1)PC・スマホ・タブレットのブラウザ上から出勤・退勤時間を打ち込んで打刻する(標準機能)
(2)社員の指の静脈を使った指静脈認証による打刻
(3)iPadを使いって社員の顔認証で行う打刻
(4)GPSの位置情報を使って行う打刻
(5)専用QRコードを社員各自に配布し、スマホでQRコード読み込んで打刻する方法
7.導入を進める際に知っておくといいこと
導入を進めていくうえで、知っておいた方がいいことをまとめましたのでご案内します。
7-1.クレジットカード一体型のICカードの利用
交通系ICカードや電子マネーには、クレジットカード機能が付いているものもあります。カードの表面にはカード番号や有効期限が記載されており初回登録や打刻の際に本人以外に見えてしまうこともあります。無用な事故につなげないためにもクレジットカード一体型のICカードは利用できないようにする等のルールを作ることをおすすめします。
7-2.入退室のICカードを活用することも
オフィスの入退室にICカードを利用している場合は、そのICカードで勤怠の登録ができる場合もあります。勤怠管理システムによって対応している場合やしていない場合もあります。入退室のICカードであれば全社員が持っていることもありますので交通系ICカードよりも取り組みやすい可能性もあります。使用している勤怠管理システムが入退室ICカードでの勤怠登録に対応できる場合はぜひご検討ください。
7-3.あらかじめ自社の運用をシミュレーションする
検討の序盤から中盤にかけて、ICカードを自社で使った場合の運用のシミュレーションをすることをおすすめします。ICカードリーダーをどこに置いたら便利か、何台必要か等によってもコストが決まってきます。また打刻忘れが無くせるような置き場所という視点でも検討してみるといいかもしれません。
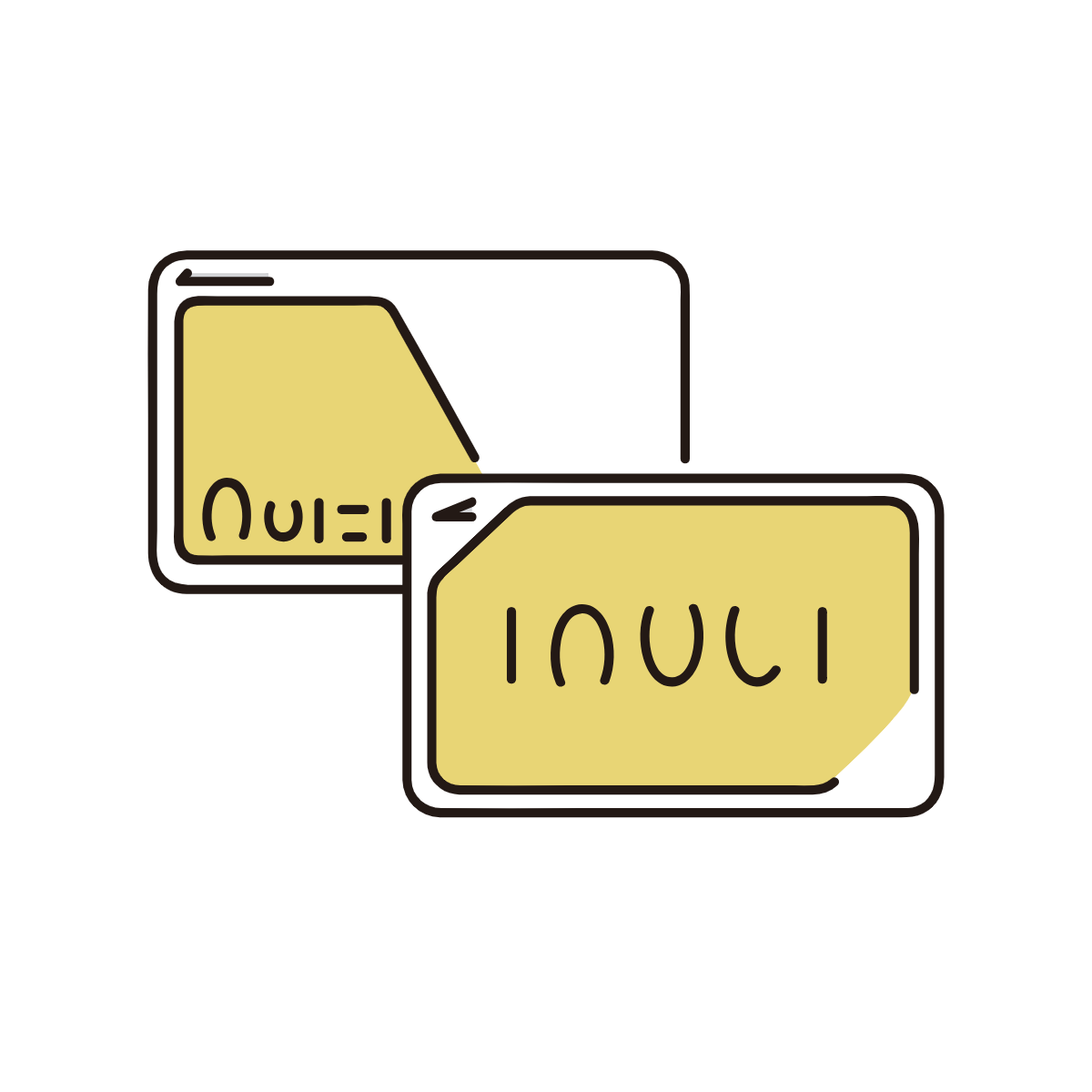
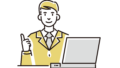

コメント