社内で蓄積されている知識やノウハウを簡単に共有する方法はないものかと、日ごろ感じている企業の管理職層の方も多いのではないでしょうか。例えば営業社員の成功事例であったり、カスタマーサービス部門の解決事例であったり、社内共有することで他の社員も業績を上げることにつながったり、会社として顧客満足度を上げていくこともできます。ちなみに既に成功事例や解決事例がエクセルやワード、パワーポイント、PDFファイルなどで社内に存在している場合は、ナレッジ共有ツールを導入することで簡単に社内に蓄積されてきた知識やノウハウを社内で共有することができます。ここでは社内でのナレッジ共有を進めたい管理職層の肩に向けて、ナレッジ共有ツールの機能や導入で得られるメリットなどをご案内いたします。ぜひこの記事を読んでナレッジ共有ツールの選定に進んでみてください。
1.ナレッジ共有ツールとは
ここではナレッジ共有そのものやナレッジ共有ツールとはどのようなものかをご案内いたします。
1-1.そもそもナレッジ共有とは
仕事で使うナレッジの意味は、社内に蓄積された知識や経験、ノウハウ、マニュアルなどを意味します。人の経験や知識に基づく付加価値のある情報なので、ナレッジを利用することで仕事を早く処理できたり、販売や案件獲得をしやすくしていくことができます。
このナレッジを社内のスタッフ間で共有していくことで経験やノウハウの属人化を防ぐことができます。社員の入れ替わりのタイミングで経験やノウハウが抜け落ちてしまうこともありますが、事業を継続・発展させていくためにもナレッジの共有は重要とされています。
なおナレッジを共有・活用していくことを「ナレッジマネジメント」とも言います。
1-2.ナレッジ共有ツールとは
ナレッジと言われる仕事上の有益な情報は、各個人のエクセルやワード、紙のノートであったり、あるいは書面ではない記憶や経験の中にあることも多いかと思います。
ナレッジ共有ツールとは、各個人のナレッジ(知識、経験やノウハウなど)をシステムで一元管理できる仕組みのことです。エクセルやワードに入れたままだと検索がしにくい問題も、ツールでの検索ならばファイル内まで検索することができます。同時にツールの利用を通じてスタッフ間で ナレッジを共有することができます。
1-3.ナレッジ共有ツールの種類
ナレッジ共有ツールはナレッジの活用の仕方によって大きく3種類に分けることができます。
1.ナレッジの蓄積・活用型
クラウド上の共有ドライブやグループウェアのファイル共有機能等を利用して、社内のナレッジを保存・活用していくものです。手軽に既存のワードやエクセルファイルをアップロードして共有することもできます。
2.FAQ型
ナレッジをツール上の機能を使ってマニュアルとして仕立てたり、社内ポータルも作成できます。ナレッジをワードやエクセルのまま見せるのではなく、社員が見やすい形に加工して見せることができるため、社内にナレッジをよりわかりやすい形で周知したい場合に活用することができます。
3.ナレッジ検索型
大量のナレッジが収まったファイルや大容量データの中から素早く検索することができます。自然言語で検索できるものもあり、資料検索から問合せログの検索までいろいろな業務で活用することができます。
2.ナレッジ共有ツールの導入メリット
ここではナレッジ共有ツールの導入メリットをご案内いたします。
2-1.社員のスキルアップにつなげることができる
社内には様々な部署や職種がありますが、それぞれの成功事例をナレッジ共有ツールに登録することで、社内の他のスタッフへ知識や経験を還元することができます。
例えば営業部門であれば、好業績を上げている営業社員がターゲットを絞り込むに行っている調査方法であったり、クライアントごとの導入好事例を共有して他の営業社員が各自の業務で活かすことができます。
2-2.仕事の属人化防止につなげていくことができる
仕事の属人化は個人で進めていく業務や、長年担当している業務で比較的起こりやすいとされています。ナレッジ共有ツールを導入すると仕事上のファイル類を社内で共有できる環境が整います。属人化している状況ではマニュアルなどが無いケースも多いかと思います。そのような場合は全社的に業務のマニュアル化を推進するなど対応が必要となる場合があります。
2-3.人材育成の時間やコストを削減できる
過去の勉強会や研修の資料や動画をナレッジ共有ツールに保管しておくことで、新入社員が入ってきた場合や異動してきた新任の社員に動画や資料による研修を行うこともできます。講師が社員であれば、動画や資料で座学を行うものの質問は別途チャットやメールなどで行うこともできます。復習も空き時間に行うことができ、ナレッジ共有ツールは人材育成にも有効活用することができます。
2-4.業務の品質向上につなげることができる
細かいことですが、マニュアルや成功事例などを共有できるようにすると、社員は必要な時はもちろんのこと、空き時間にも確認することができます。業務でナレッジを使う習慣ができるため、業務知識が付いて業務の品質向上につなげていくことができます。
3.ナレッジの具体的な例
ここではナレッジ共有ツールを導入した場合にどのような情報を保存するか部門ごとに例をご案内いたします。
3-1.営業部門のナレッジ
成功・失敗事例:過去の提案書、勝敗分析、価格分析
顧客情報:ターゲットリスト、決裁者情報、過去の商談情報、クレーム対応記録
商談関連:トークスクリプト、過去の価格交渉記録
競合情報:コンペの際の競合他社の価格帯・差別化情報
営業ツール:提案書のテンプレート、見積書のフォーマット
3-2.マーケティング部門
市場調査データ:顧客ニーズ調査結果、マーケット調査結果
キャンペーン事例: 過去の販促企画の効果、改善ポイント
顧客分析:ターゲット顧客リスト、過去の購買パターン
広告分析結果:クリエイティブ別、ターゲット別の効果検証データ
3-3.カスタマーサービス部門
FAQ・対応事例:よくある質問と回答例、クレーム時の対応事例
エスカレーションの基準:上位者への引き継ぎタイミング、その際の共有方法
サービス・商品知識:商品カタログ、マニュアル、トラブル対応資料
システム操作:CRMやコールセンターシステムの使用マニュアル、案件ごとのデータ入力ルール、レポート作成手順
3-4.総務部門
規程:就業規則、賃金規定、評価規定、出張規定
申請書:各種申請書類
人事労務:雇用契約書、退職書類、労務トラブル対応事例、
オフィス管理:設備メンテナンス業者情報、備品調達先、座席表
法務情報:契約書雛形、コンプライアンス教育資料
危機管理:緊急連絡先一覧(社内・社外)BCP(事業継続計画)、災害対応マニュアル
3-5.経理部門
業務手順書:経費精算マニュアル、勘定科目マニュアル、会計システム操作マニュアル、データバックアップマニュアル、税務申告時・監査時対応マニュアル
会計処理事例:減価償却方法、特殊取引の仕訳例、マニュアル
内部統制関連:チェックリスト、承認フロー、不正防止対策
4.ナレッジ共有ツールの機能
ここではナレッジ共有ツールの機能をご案内いたします。
4-1.ファイル共有機能
ワードファイルやエクセル、パワーポイントなど社内にある既存のファイルを共有する機能です。社員がダウンロードやアップロードを行うことツール上で社内に共有することができます。
4-2.検索機能
ナレッジ共有ツールに入れたワードやエクセル、PDFなどのファイルは、高速に検索することができます。検索はファイル名を検索するだけでなく、ファイルの中(例えばワードファイルだと文書の中身)の文字まで検索することができます。
4-3.オフィスソフト機能
Google WorkspaceやMicrosoft365などは、共有ツール上でオフィスソフトを開いてワープロ、表計算、プレゼンテーションソフトを社員同士が共同編集することもできます。オフィスソフト機能を使ってマニュアルやFAQを追記しながら運用する場合は、ツール上でマニュアルやFAQを直接編集できるため効率的に業務を行うことができます。
4-4.マニュアル作成機能
ナレッジ共有ツール上にあるマニュアル作成機能を使うと、手早くマニュアルを作成することができます。画像の貼り付けや文字サイズの変更など一般的なワープロソフトの基本操作は可能で、社内で統一フォーマットのマニュアルを作成することもできます。
4-5.FAQ作成機能
FAQを1問1答式で質問とそれに対する答えの形式で作成することができます。このFAQ作成機能は、カスタマーサポートの社員が顧客に回答する際にも有効な機能です。ナレッジ共有ツールはもともとナレッジを見やすく表示させるようにデザインされているので、質問と答えを打ち込んでおくと見やすく画面上で表示することができます。
4-6.権限管理機能
社員ごとやファイル・フォルダごとに閲覧権限を設定することができます。閲覧できる社員とできない社員で管理したいファイルについてはきちんと管理できるので、部署内に限定してファイル共有を行うなども可能です。またファイルにダウンロード制限を課すことも可能で、制限を有効にするとナレッジ共有ツール上でプレビューのみ行いファイルのダウンロードは不可能にする制限を加えることができます。
5.ナレッジ共有ツールの課題・デメリット
ここではナレッジ共有ツールの課題・デメリットをご案内いたします。
5-1.共有する情報の量や質は管理が必要
ナレッジ共有ツールはいわば「大きな空の箱」です。利用するには、社員がナレッジをツールに登録していく必要があります。
これまでナレッジ共有は進んでいなかった会社でツールの導入を行った場合、社員によっては必要性や意義を理解できずにナレッジをあまり登録しない場合もあります。そのため登録されるナレッジの量や質については、ナレッジ共有ツールの活用にも関わるので、特に初期は十分であるか確認、管理していく必要もあります。
5-2.社内に共有文化も必要
社内にナレッジを共有する文化が定着している企業というのは、会社のカルチャーとして既に共有文化が浸透している企業とも言えます。
どの部門でも言える事ですが、例えば営業部門では好業績を上げる社員の営業の秘密は、社内で競争しているのでその本人からすると「教えたくない」と感じてしまうケースもあります。もちろんその逆で自分のノウハウが役に立つならと共有を快諾するケースもあるでしょう。このように共有文化が定着していない組織では、成功事例などの共有が進まないことがあります。共有文化も企業文化の一つとして何度も繰り返し発信していくことで定着させていくこともできるのではないでしょうか。
6.代表的なナレッジ共有ツールのご案内
ここでは代表的なナレッジ共有ツールをいくつかご案内いたします。
| 区分 | サービス名 | 提供元 |
| ナレッジの蓄積・活用型 | Google Workspace | |
| Microsoft 365 | マイクロソフト | |
| サイボウズ Office | サイボウズ株式会社 | |
| rakumoボード | rakumo 株式会社 | |
| QiitaTeam | Qiita株式会社 | |
| FAQ型 | NotePM | 株式会社プロジェクト・モード |
| kintone | サイボウズ株式会社 | |
| アルファスコープ | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | |
| ナレッジ検索型 | QuickSolution | 住友電工情報システム株式会社 |
| Liferay DXP | 日本ライフレイ株式会社 |
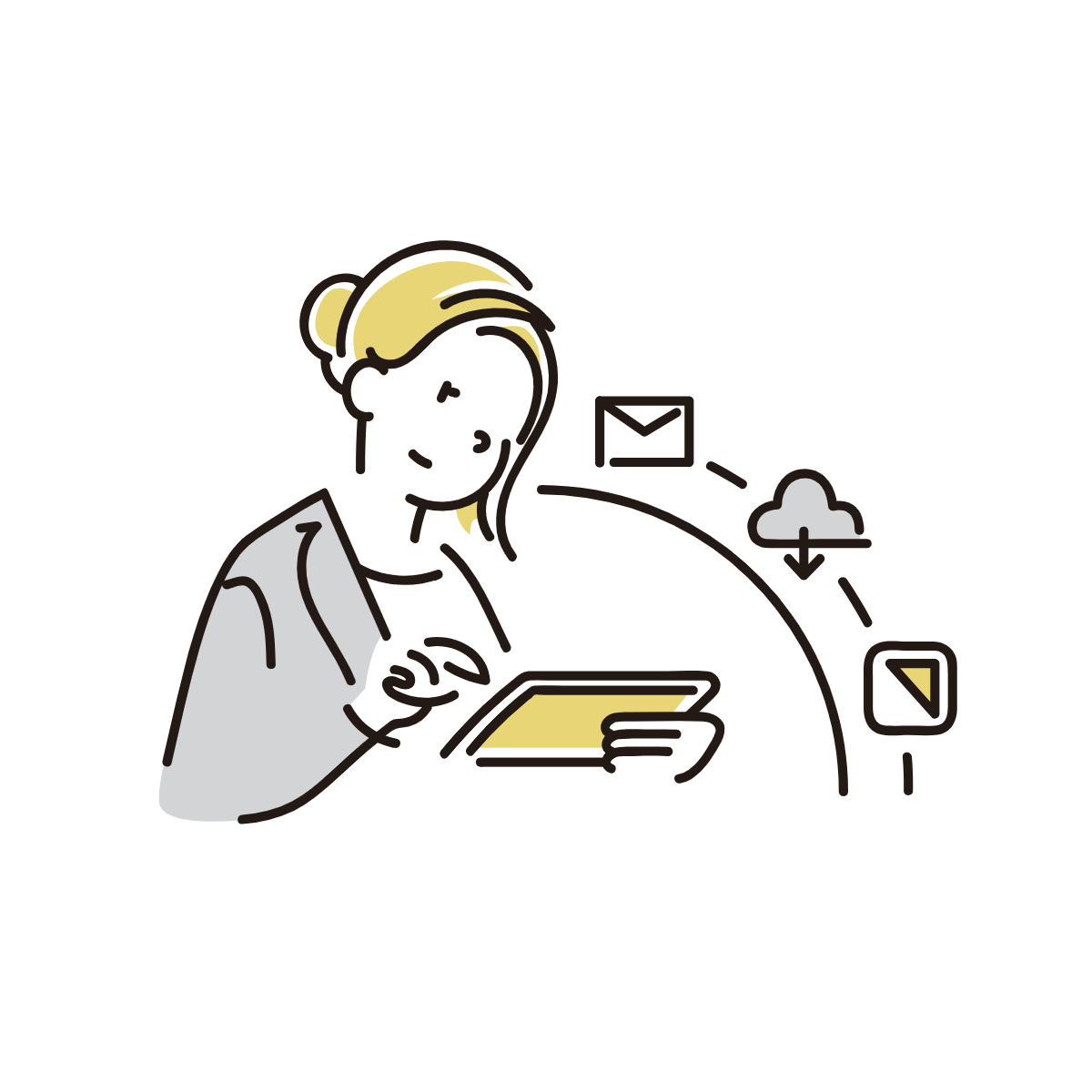
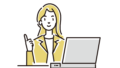
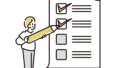
コメント