これまで法律により従業員へのストレスチェックの実施は50名未満の事業所では免除されていましたが、2025年5月に法律が改正され、今後は50名未満の事業所でもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。これまでは大企業・中規模企業に義務の対象となっていましたが、これによりすべての企業でストレスチェックを実施することが義務付けられたことになります。法律の施行は先のようですが、中小企業で労務管理を担当する方や経営者の方へ向けこの記事で、そもそもストレスチェックとは?からストレスチェックシステムを導入すると手間を減らして実施できることまでご案内いたします。ぜひストレスチェックシステムの導入に向けシステム選定に進んでみてください。
1.ストレスチェックとは
ストレスチェックとはどのようなものか、対象となる企業やどのようなことを行うのかを簡単にご案内します。
1-1.ストレスチェックとは法で企業に義務付けられた検査
ストレスチェックとは2015年に労働安全衛生法で新たに規定された、従業員のメンタルチェック等を実施する義務のことです。2015年に制定された法律では企業に対して、50名以上の従業員が働く事業所での検査を義務付けており、企業は年に1回以上のストレスチェックの実施が必要となっています。
ちなみに義務はありませんが50名未満の事業所でもストレスチェックを行うことは全く問題なく実施できます。(正確には50名未満の事業所にはストレスチェック実施は努力義務となっており義務ではありません)
1-2.義務の対象外だった50名未満の事業所でも2028年より義務化される
50名未満の従業員が働く事業所では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていましたが、2025年5月に50名未満の事業所へのストレスチェック実施の義務化が法改正されました。施行は準備期間を置いたうえでとされており、2028年頃とみられますが50未満の事業所にもストレスチェックの義務化が実施されることが考えられます。
1-3.ストレスチェックが法で義務付けられた背景
職場でのストレスが原因でうつ病などの精神的な病気になることは大分以前より問題になっており、厚生労働所では2006年に労働者の心の健康保持増進のための指針を定めて、職場でのメンタルヘルス対策を促進してきました。その後もストレスが原因で労災認定される数は増加傾向は変わらず、厚生労働省は2015年に労働安全衛生法を改正して、50名以上が働く事業所でのストレスチェックを企業に義務付けました。
1-4.ストレスチェックとは企業はどのようなことを行うのか
厚生労働省によると、ストレスチェックは以下の手順で行うとされています。1~4は全員に対して行いますが、5~8はストレスが高い人のみに行います。
- 導入前の準備(実施方法などの社内ルール策定)
- 質問票の配布・記入 ※システムで実施してもOK
- ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否判定
- 本人へ結果を通知/会社で部署ごと・年代等で集計分析を行い職場環境を改善
- 本人から面接指導の申し出
- 医師による面接指導の実施
- 就業上の措置の要否や内容について医師から意見聴取
- 就業上の措置の実施
- 「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止
ちなみにストレスチェックの終了後は労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。
厚生労働省のサイトにわかりやすい資料があります。
詳しくはこちらへ⇒e-ラーニングで学ぶ 15分でわかる 法に基づくストレスチェック制度(厚生労働省)
2.ストレスチェック システムとは
ここではストレスチェックシステムとはどのようなものかや、システムの導入でストレスチェックの手間が削減できること、ストレスチェックシステムの種類をご案内します。
2-1.ストレスチェックシステムとは従業員からの回答受付や分析を行うもの
ストレスチェックシステムとは、労働安全衛生法で企業に義務付けている従業員へのストレスチェックを効率的に行うシステムです。ストレスチェックシステムを導入すると、従業員はストレスチェックの回答サイトへログインして質問票を確認してその場で回答をしていきます。結果は自動でシステムが集計・分析を行うため、従業員とのストレスチェックやり取りをペーパレスで効率的に行うことができます。
2-2.ストレスチェックシステムの種類
ストレスチェックシステムは「ストレスチェック単一機能型」「労務管理システムとの連携型」2種類あります。どちらの種類にも従業員への質問・回答受付や結果の分析などを行うことができます。
ストレスチェック単一機能型は、ストレスチェックに必要な機能だけが搭載されたシステムです。従業員の情報や部署の情報を入力することで、質問票の配布や回答依頼を行うことができます。代表的なシステムの例では「ストレスチェッカー」「Co-Labo」「ORIZIN」「STRESS CHECK SYSTEM」などがあります。
労務管理システムとの連携型は、現在自社で労務管理システムを導入しており、その労務管理システムにストレスチェック機能が付いている場合に利用できます。既に労務管理システム内に社員情報や部署情報があるため、社員情報の二度打ちは不要でストレスチェックを行う際も対象の社員や部署を選ぶような操作をするだけで始めることができます。代表的なシステムの例では「SmartHR(Stress Checkerとの連携で実現)」や「ジョブカン」が上げられます。自社にこれらの労務管理システムが導入されている場合は、手間が削減できるためストレスチェック機能も利用することをおすすめします。
3.ストレスチェックシステムの機能・サービス
ここではストレスチェックシステムの機能・サービスについてご案内します。
3-1.ストレスチェックの質問票・回答受付機能
質問は、ストレスチェックシステム側であらかじめ用意されており、基本的には独自の質問を作成しなくても調査を実施することができます。質問数は57問と80問の2通りあることが多く、57問の質問では厚生労働省が推奨する標準的なストレス状態の把握を目的としています。80問の質問では、57問の質問に加えて職場状況の改善を目的とした質問項目が追加されています。特段追加の質問を設けなくてもストレスチェックシステム側で制度の趣旨に応じた質問は用意されています。また、ストレスチェックシステムによっては追加で自社独自の質問を加えられるものもあり、自社で聞きたいことがあれば質問を埋め込むことも可能です。回答はWEBブラウザ上で行うため、PCで業務を行っていれば問題なく回答はすることができます。
3-2.集団分析機能
ストレスチェックでは個人の回答結果を一定規模の集団ごとに集計・分析することも求めています。これは例えば部署ごとであったり職種ごとに分析することを表しています。
ストレスチェックシステムには最初から分析機能が用意されており、現在の仕事内容についての回答やストレス反応についての回答、周囲のサポートについての回答などを会社全体であったり部署ごとで集計した結果を確認することができます。
3-3.個人結果の分析機能
ストレスチェックをWEB上で回答した従業員は基本的にはその場で回答者個人の分析結果を確認することができます。
個人分析結果には、厚生労働省により以下の1~3の項目は必ず通知しなければならないとされています。4・5の項目は本人への通知が推奨されているものです。
- 個人のストレスプロフィール
- ストレスの程度
- 面接指導の対象者か否かの判定結果
- セルフケアのためのアドバイス
- 会社への面接指導の申し出窓口
ちなみに、ストレスチェックの個人分析結果を見られるのは厚生労働省によって回答者本人とストレスチェック実施の事務担当者のみとされています。事務担当者が見れるというのは個人結果を本人に返すための事務作業で目にすることがあるためです。そのため会社が個人の分析結果を見るということは回答者個人から同意がない場合はできないように規定されています。回答者個人から同意を得られれば会社で個人分析の内容を確認することもできます。
4.ストレスチェックシステムの導入メリット
ここではストレスチェックシステムの導入メリットをご案内します。
4-1.準備から回答までストレスチェックを簡単に実施できる
ストレスチェックシステムにはあらかじめ従業員への質問が設定されており、特段質問を打ち込むといった作業は不要になっています。また従業員が回答すると個人の分析結果が自動で回答後の画面に表示されるようになっており、分析も自動で行われます。ストレスチェックの実施に当たっては基本的にストレスチェックシステムには社員情報や組織情報を事前登録する程度で済むため、ストレスチェックシステムにより人事労務の担当者の手間もあらかじめ省かれています。
4-2.集団分析も簡単に行うことができ、データをもとに社内で改善施策も検討できる
集団分析の集団とは、部署や年代、性別など、ストレスチェックの結果をどんな単位で集計して見るかを表しています。ストレスチェックシステムの準備を行う際に、従業員の氏名と同時にその従業員の部署名や年代、性別、役職なども併せてシステムへ入力します。ここで入力しておいた氏名以外の例えば年代30代だけの検査結果を集計すると、これも例ですが「30代の従業員は仕事量は多いと感じている人が多く、上司の支援を受けられている人が少ない」というような分析結果も見ることができます。
なお、個人結果の分析機能の箇所でもお伝えしましたが、ストレスチェックは国の方針もあり従業員の同意がない場合は、結果の分析においても個人が特定できるようなことはしてはいけない事とされています。そのため分析でも例えばある3人の部署で男性1名女性2名という集計をすると、男性1名はほぼ氏名を特定できてしまいます。このように細かすぎる集計をしてしまうと本人の特定ができてしまうため、担当者の方は集団分析の運用にも少し気を配る必要があります。
4-3.オプションサービス
ストレスチェックシステムによっては、以下のようなオプションサービスを提供していることがあります。
- 紙用紙でのストレスチェックの実施
PCがない場合や操作が難しい場合の想定となりますが、ストレスチェックシステムの提供会社によってはマークシート方式等の紙のストレスチェック用紙を用意していることがあります。 - 独自質問の追加
ストレスチェックの質問は最初からシステムへ登録されていますが、自社独自の質問を組み入れたい場合に有料で追加できる場合があります。 - 集団分析へ独自項目の追加
集団分析の際に決まったフォーマットの分析以外は有料で対応する提供会社もあります。 - 高ストレス者の医師面談の実施
医師は産業医へ依頼するのが通常かもしれませんが、ストレスチェックシステムの提供会社によっては、システム会社がオンラインでの医師面談を有料で用意することもできます。
5.代表的なストレスチェックシステムのご案内
ここでは代表的なストレスチェックシステムをいくつかご案内します。システム名をクリックするとそのシステムの公式サイトへリンクします。
| 区分 | システム名 | 提供元 |
| ストレスチェック単一機能型 | ストレスチェッカー | 株式会社HRデータラボ |
| Co-Labo | 株式会社ヒューマネージ | |
| ORIZIN | ピー・シー・エー株式会社 | |
| STRESS CHECK SYSTEM | 都築電気株式会社 | |
| 労務管理システムとの連携型 | SmartHR (Stress Checkerとの連携) |
株式会社SmartHR |
| ジョブカン | 株式会社DONUTS |


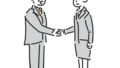
コメント