テレワークを行う際に「労働時間をきちんと把握できていない」「打刻された労働時間の中できちんと業務を行っているかわからない」など勤怠管理の悩みを持つ労務管理担当の方も多いのではないでしょうか。
そんな労務管理担当の方に向けて、ここではテレワークの労働時間にまつわる課題の解決方法や、テレワーク時の業務内容を見える化する管理方法、それらを実践していくために必要なシステムをご案内します。
この記事を読んで自社のテレワークでの勤怠管理の課題解決に向け、ぜひ必要となるシステムの選定に進んでみてください。
1.テレワークでの勤怠管理とは
ここではそもそも勤怠管理とは何なのかや、勤怠管理を大切にすべき理由、テレワークでの勤怠管理とは何なのかなどをご案内します。
1-1.そもそも勤怠管理とは
テレワークでの勤怠管理について深堀していく前に、まずは勤怠管理とは一体何なのかについてご案内したいと思います。
そもそも勤怠管理とは、仕事において会社が従業員の「勤めること」と「怠けること」を管理することです。勤めるは理解できても、怠けるはあまりイメージがわかないかもしれませんが。怠けるからは例えば欠勤や(意味が広いですが)休暇などが連想できるのではと思います。まず言葉としての勤怠とは、勤めることとその真逆の怠けること、その両極をくっつけて両方を表現できる言葉と言えます。
前置きが長くなってしまいましたが、具体的な労務管理業務に落として表現すると勤怠管理とは給与計算や労働法令規制を遵守するために出勤時間や退勤時間を記録して出勤日数や出勤時間を算出して管理することです。また有給休暇や欠勤など休みの管理も給与計算等にも必要なため勤怠管理の中に含まれています。
1-2.勤怠管理を大切にしなければならない理由
企業は、規則に従って給与を計算し支払うためなどの理由で自社の従業員の出勤・退勤・休暇をはじめとした勤怠管理を行っていかないとならないわけですが、この行為はきちんと法令で企業の義務として規定けされています。具体的には労働基準法で、企業は正確な従業員の労働時間、日数、残業時間、深夜残業時間などを把握して賃金計算を行う台帳に記入することが求められています。
1-3.(補足)給与計算業務も勤怠管理の情報を利用して行う
この勤怠管理で整理した社員の勤務日数や休暇・欠勤日数を利用して実際の給与計算業務も行われます。その計算例をご案内したいと思います。
通常は、社員の月給はあらかじめ月に●●万円と決まっています。一般的にはこの金額に残業をした場合は残業代が加算されて給与が支払われています。
例えば、欠勤がなく1ヵ月の出勤日を毎日出勤するか、一部有給休暇を取得して残りは出勤していた場合は、月給●●万円(+残業代)がそのまま給与として支払われます。
もし、欠勤が1日あった場合は、1カ月の出勤日が20日とすると、欠勤した日数分の給与(月給の1/20の額)を差し引いて、その月の月給は19/20の額(+残業代)で支給されます。
1-4.テレワークにおける勤怠管理とは
これまで勤怠管理は労働基準法で課された企業の義務で、企業は勤怠管理で算出した労働時間等を利用して給与計算や残業時間の管理をしていることをお話ししました。
実はここでいう労働時間というのは、(厚生労働省のガイドラインを要約すると)出勤と退勤の時間からただ労働時間を算出して記録するという意味ではなく、その時間内に企業が指示した業務を行っている時間を意味します。
これはどういうことかというと、いわゆる「ヤミ残業」で正規の労働時間をすべて反映できていないことや、逆に実態として労働を行っていないのに正規の労働時間に反映されてしまっているということを意味します。
従業員の労働時間や業務内容の管理は所属する部署の管理職がを行うのが通常です。従業員と管理職が同じ事務所で働いている場合は、そのおかげで出勤しているか、残業申請が出ているか、働いている時間通りに残業実績が付いているか、会社の業務を明示・黙示で行っているかなど(前出の労働時間のガイドラインでは管理職が現認するとされている)、管理職が確認して勤怠管理も問題なく行っていくことができます。
しかしこれがテレワークとなると、従業員と管理職が同じ場所にいない分、出勤や退勤、会社の業務を行っているかも本人の申請頼りになってしまいます。テレワークにおける勤怠管理とは、この申請だよりの出勤や退勤、会社の業務の管理職による現認をどうやっていくか(ルールを)定義して、実践していくことを意味します。
2.テレワークの出勤・退勤打刻(労働時間)にまつわる課題の解決方法
実際に顔をあわせないテレワーク環境で、出勤や退勤が行われたことをどのように管理職が確認していくかについて事例をご案内します。以下のいくつかある解決方法の中から1つ実践するか、あるいは2つ以上を組み合わせて実践するか検討する必要があります。
2-1.(必須)出勤時間や退勤時間を従業員自ら申請する
テレワークでは従業員に出勤時刻や退勤時刻を自ら申請して、この時刻に対して管理職が確認を行っていくことを中心にすえます。事務所ではタイムカードなど紙の勤怠管理を行っている場合は、この時間の本人申告は出勤時間や退勤時間の打刻と同じ意味を持ちます。従業員も管理職もなるべく負荷をかけないため出勤退勤時間の申請は勤怠管理システム上で行うことをお勧めします。※紙で勤怠を行っている場合はこの機会に勤怠管理システムを導入検討ください。
2-2.チャット等で始業や終業のメッセージを送信する
もっとも簡単な出勤や退勤の確認方法ですが会社でビジネスチャットを導入している場合はメッセージを送る確認方法があります。チャットであればリアルタイムに送信されるため、従業員も管理職も手早く出勤の確認を完了させることができます。チャットだけでは従業員がどこにいるかは判別がつかないため、次のGPS打刻とあわせて採用するかなども検討する必要があります。
2-3.GPS打刻に対応した勤怠管理システムを利用して従業員はスマホ打刻する
従業員がスマートフォンを使って打刻する方法です。GPS打刻に対応した勤怠管理システムが導入されている必要がありますが、この方法を使うとスマホで打刻する際の位置情報を出勤・退勤時間と共に記録します。管理職は従業員が打刻時点で居た場所を確認することができ、申請通りの場所で業務体制に入ったり、終業したりといったことは管理することができます。
⇒GPS打刻についてはこちらの記事「GPSを使った勤怠管理で不正や打刻忘れを防止!GPS打刻の導入方法案内」で詳しく説明しています
2-4.朝夕にリモート朝礼やリモート夕礼を行う
テレワーク時には会社のノートPCを貸与している場合がほとんどと思いますが、ノートPCに付いているカメラを使い朝夕にリモート朝礼や夕礼を行うことで勤務の開始や終了を確認することもできます。この方法は、人が各地に散って勤務していることが多い組織では特に有効です。カメラを使うことで健康状態の確認も兼ねることもできます。
2-5.端末管理ソフトを利用する
PCに端末管理ソフトを入れて従業員が実際に端末を操作しているか確認することで出勤や退勤を確認する方法です。キーボードの使用数やマウスの移動距離、アプリケーションの利用時間などのデータで実際に勤務が開始した、終了したかを確認する方法です。
3.テレワーク時の業務内容が見えずらい課題の解決方法
テレワーク時の業務内容が見えずらい課題というと、ちょっと遠回しでわかりにくいかもしれませんが、PCに向かって通常通り仕事を行っているか否かを知ることです。事務所で勤めていると長時間離席していることは見ればわかりますが、テレワークだと物理的に業務を行っているかは見えません。そのためテレワークでは、この見えにくい「働いていること」をどのように見える化するかの事例をご紹介します。
3-1.スケジューラーやタスク管理ツールを導入する
基本的な業務内容の管理方法となりますが、スケジューラーへの予定の登録であったりタスク管理ツールへ業務をタスクやアクション単位で打ち込み、かかった時間を入力するといったものがあります。スケジューラーは将来の業務予定で、タスク管理ツールが過去の業務実績という位置づけです。これらはテレワークを行う個人にだけ登録を絞ってしまうよりも、部課内でスケジューラーやタスク管理ツールを運用して部課内の仕事の流れや進捗を見えるように出来るとより一層タスク登録も円滑に進ませることができます。
3-2.端末管理ソフトを利用する
これは勤務の開始や終了の時刻を確認する方法としてもご紹介しましたが、業務内容の管理でも利用することができます。この端末管理ソフトがPCにインストールされていると、従業員がPC上で行う操作が記録されるため明確にPC操作しているか確認することができます。具体的にはどのようなソフトをどれくらいの時間使っているか、キーボードの打ち込み回数やマウスの移動距離などが確認できます。またキーボードやマウスの未操作時間により、稼働、離席、休憩、非稼働の割合を出すこともできます。
4.テレワークで有効な勤怠管理を行っていく方法(まとめ)
ここではテレワークで有効な勤怠管理を行っていく方法をご案内します。
4-1.勤怠管理システムを利用する
テレワーク下で労働時間管理をしていくには、勤怠管理システムを利用していくことが必須と言えます。
1つ目の理由は出勤・退勤・残業の申請や承認が従業員も管理職もPC上の操作で簡単に申請・確認できるためです。紙のタイムカードを基本にしていると、勤務時間や残業時間の反映が後になるため残業可否の判断を行う場合も過去の残業の状況を見逃しがちになってしまいます。本来発生の都度すべき勤怠申請と承認もシステム上で処理することで速やかに従業員も管理職も対応することができます。
2つ目の理由はスマホを利用したGPS打刻ができることです。GPS打刻に対応している勤怠管理システムであれば出勤や退勤をどこで行ったかを確認することができるため、事務所以外のところで勤務する・したことの証とすることもできます。
4-2.コミュニケーションツールや端末管理ソフトを利用する
テレワークで業務内容を管理していくには、コミュニケーションツールの導入は必須と言えます。端末管理ソフトは可能なら導入すべきです。
ここではコミュニケーションツール自体は、むしろテレワークで業務を行う上で最低限必要なインフラという位置づけでお話しています。例えば、Microsoft TeamsやGoogle Workspaceなどを導入すると、チャットはもちろんのこと、事務所とテレワークをつないで画面共有することもできます。そのため事務所で仕事をしている時のように新しい業務方法をメンバー同士でまとめるミーティングを画面共有を使って行うこともできます。こういったコミュニケーションツールがあることで、業務内容の管理以前に、リモートで働く環境の整備をすることができます。あとは業務の内容の成果物を確認したり、管理する従業員数が多い管理者や多忙な管理者など必要であれば端末管理ソフトの導入を行うことも有効です。
5.テレワークの勤怠管理課題の解決に向けて使用できるシステム
| 区分 | サービス名 | 提供元 |
| 勤怠管理 | KING OF TIME | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| jinjier勤怠 | jinjer株式会社 | |
| スマレジTIME CARD | 株式会社スマレジ | |
| コミュニケーションツール | Microsoft 365 | マイクロソフト |
| Google Workspace | グーグル | |
| PCログ管理 | ジャスミー | ジャスミー株式会社 |
| LANSCOPE | エムオーテックス株式会社 |
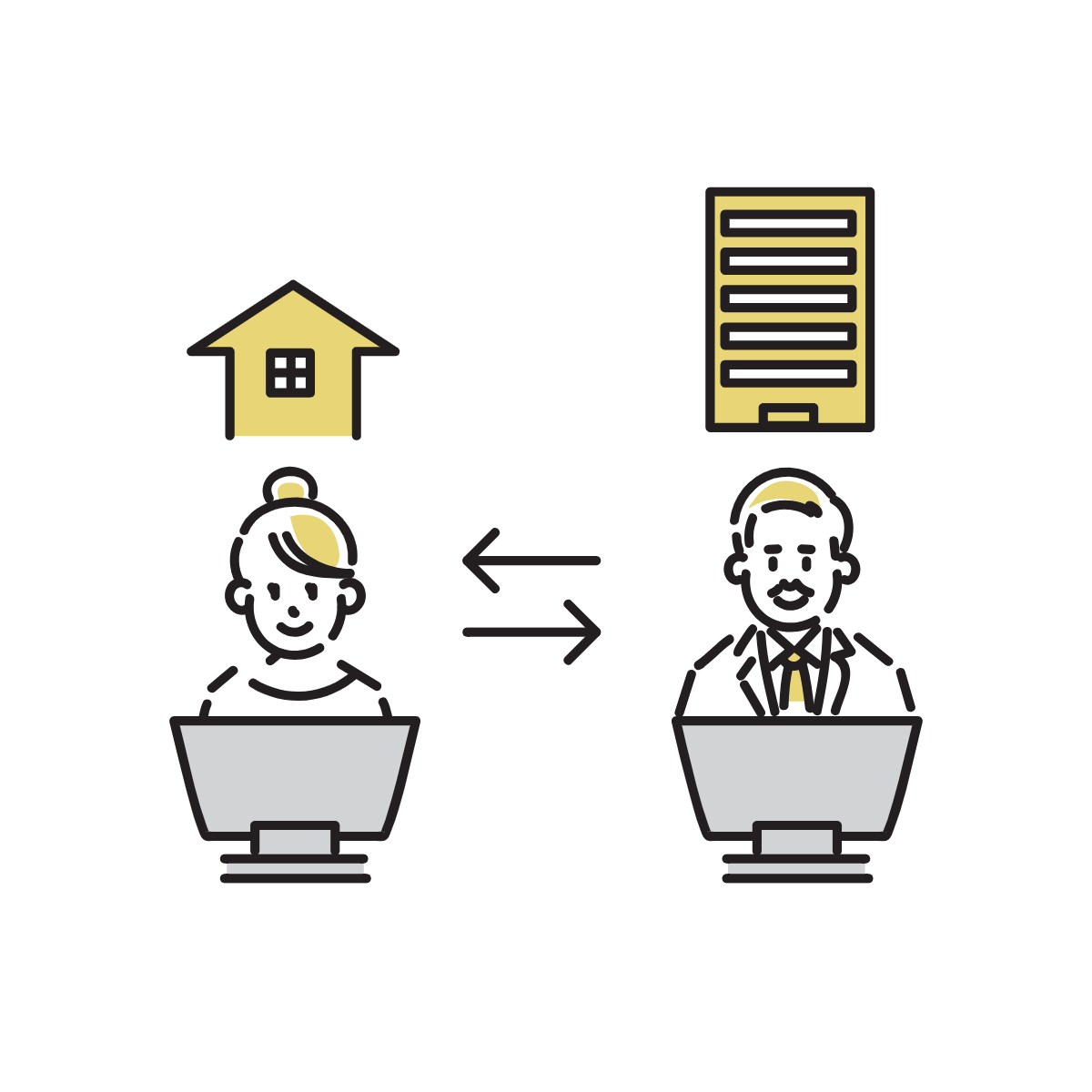
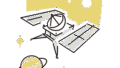
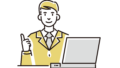
コメント