ネットワークカメラやIoT機器を使いたいので屋外や工場・建物内でなるべくコストをかけずに通信ネットワークを構築したい。そんな課題をお持ちの中小企業のシステム担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この課題に対して1km近い通信距離を持つ長距離無線LAN(Wi-Fi HaLow IEEE 802.11ah)を導入することで解決できる可能性があります。長距離無線LANには、通信仕様がIoT機器向けではあるものの1km近い通信距離が利用でき、かつ障害物を回り込みやすい周波数帯を使っているため、冒頭の用途であれば運用ができたりコスト面でもメリットを出せる場合があります。ここでは広い場所での通信環境整備に課題を持つ中小企業のIT担当の方に向けて、長距離無線LANとはどのようなものかや、屋外利用や免許不要で利用できる根拠、利用事例、メリット、デメリットをご案内いたします。ぜひこの記事を読んで、用途が通信仕様と合う場合は、通信インフラ整備の際の候補に入れてみて下さい。
1.長距離無線LANとは
ここでは長距離無線LANとはどのようなものか、まず最初に知っていただきたいことをご案内いたします。
1-1.そもそも長距離無線LAN(Wi-Fi HaLow IEEE 802.11ah)とは
長距離無線LANとは、通常のWi-Fiであれば最大でも100m程度の通信距離となるところを1km程度の無線LANとしては非常に長い通信距離で利用できるLANのことです(条件によって距離は数百メートルから1.数キロに前後します)。無線LANの規格としては、Wi-Fi HaLow(読み方:ワイファイ ヘイロー) IEEE 802.11ahと言われています。LANケーブルを利用しても基本的に100m程度(エクステンダーを利用するともう少し伸ばせる場合がある)しか通信距離を伸ばせないため、工場や屋外などある程度物理的に長い距離が離れている状況下でIoT用途などでネットワークを整備したい場合には有効な通信手段となります。※オフィス内に整備すれば通信範囲が広がるためプリンターやスキャナーの置き場所も自由に決められる可能性もあります。
なぜIoT用途などかと言うと、この長距離無線LANのIEEE802.11ahは、送信時間が一定時間内の10%までという制約があるためです。これは電波法によりIEEE802.11ahでの通信は他の無線通信との干渉を防ぐために送信時間を全体の10%(Duty比10%、1時間あたり送信が360秒まで)以下にするよう規制されているためです。
そのため比較的長距離通信が必要な防犯目的をはじめとするIoT機器などで比較的活用されています。
ちなにみ長距離無線LAN(IEEE 802.11ah)は920MHz帯を使うため、携帯電話のプラチナバンドのように障害物を回り込む特性があり、接続機器も電波をつかみやすいとも言えます。
1-2.長距離無線LANの特徴
この長距離無線LAN(Wi-Fi HaLow IEEE 802.11ah)は、1km前後の通信距離を出せることがあるため、離れた場所とネットワークを結ぶ必要がある際に重宝する通信規格となります。基本的にはIoT用途が多くなりますが、以下のような特徴を発揮します。
・設置が比較的しやすいこと
無線通信であるため、LANケーブルの敷設と比べると距離が長い場合でも、地形に起伏がある場合にも通信機器を設置がしやすい面の特徴があります。LANケーブルの場合は100mおきにエクステンダーの設置が必要だったり、敷設や固定や防水の工事も必要です。長距離無線LANであれば、アンテナの据え付け工事を行うことで利用することができるため、特に屋外ではLANケーブルに比べると容易に設置することができます。
・更に距離の延長も可能なこと
長距離無線LANでも中継器を設置することで、さらに広範囲で通信を行うことも可能となります。LANケーブルであると100mおきにエクステンダーとLANケーブルを継ぎ足して延長することになるため、長距離無線LANであれば中継器の設置だけで済むため通信距離の延長もしやすくなっています。
・費用の合理性もあること
LANケーブルを敷設する場合は、距離が長くなるほど設置や防水工事、材料にかかるコスト面が大きくなってしまいます。ですが長距離無線LANであれば、基本的にアンテナの設置工事(要電源)で済むため費用的にも安く収められる場合があります。
1-3.長距離無線LANの用途
ここでは長距離無線LANの用途を簡単にご案内いたします。
・様々な場所でのネットワークカメラでの利用
広い工場内でネットワークカメラの映像を伝送する際にも長距離無線LANを整備すれば、比較的広い範囲に設置することが可能です。またダムの内部であったり、山間部の河川を含めた携帯電話通信の不感地帯でのネットワークカメラなどでも利用する例があります。
・地下などでの建設現場や採掘施設、広い工場内での業務データ管理での利用
建設現場や採掘施設で利用している主にはIoTセンサーが対象となりますが、業務データ収集に利用する例があります。
・インフラのIoTセンサーでの利用
地下の水道施設で水位計のIoTセンサーを利用する際に、収集するデータを送信するために利用する例があります。
1-4.その他の無線LAN通信規格との比較
ここではそのほかの無線LANの通信規格と長距離無線LANの企画を比較いたします。
| 項目 | IEEE 802.11ah | 従来規格(11n/ac/ax) |
| 周波数帯 | 900MHz帯 | 2.4GHz/5GHz |
| 最大通信速度 (おおよその規格値) |
最大150Mbps | 最大9.6Gbps(11ax) |
| 目安通信距離 | 1km程度 | 100m程度 |
| 消費電力 | 低消費電力 | 通常消費電力 |
2.長距離無線LANの屋外利用と電波法での免許の位置づけ
ここでは長距離無線LANの屋外利用と電波法での免許の位置づけについてご案内いたします。
2-1.長距離無線LANの屋外利用は電波法で認められている
長距離無線LANのWi-Fi HaLow IEEE 802.11ahでは、920MHz帯を利用するため、電波法で屋外利用することは可能になっています。
屋外利用できない周波数帯は5.2Ghz帯と5.3Ghz帯のため、長距離無線LANであれば問題なく屋外利用することができます。
2-2.長距離無線LAN(920MHz帯)の利用に免許は不要
長距離無線LAN(920MHz帯)を利用する場合ですが、基本的にIoT機器のデータ伝送用に使う場合は電波法で免許は不要になっています。
3.今後利用も含めて利用が想定される長距離無線LANの利用シーン・事例
ここでは今後も含めて利用が想定される長距離無線LANの利用シーンや事例をご案内いたします。
3-1.工場や公共施設などの防犯カメラでの利用
工場や公共施設は建物が比較的広いため、一般的な通信範囲100m程度のWi-Fi規格のアクセスポイントを整備していると非常に多くのアクセスポイントが必要となりWi-Fi整備の費用もかさみがちになります。そのためこういった広い場所を持つ建物では、(一番多い利用シーンかもしれませんが)長距離無線LANの通信範囲が広い特性を活かして防犯カメラの映像伝送に利用することができます。映像は帯域を食うため、長距離無線LANでは電波法で全体時間の10%以上の送信ができないため、カメラのビットレートを可変にしたり、ルーターの設定を調整するなど設定値を詰める必要もあります。
3-2.電波の回り込み特性を活かした病院や老人施設などでの利用
長距離無線LANは920Mhz帯を使うため電波が障害物を回り込む特性がありアクセスポイントの設置箇所も少なくすることができます。そのため複数のフロアでIoT機器を利用する病院であったり老人ホームでも今後は利用する機会が増えてくるものと考えられます。
3-3.山間部の工事や鉱山など携帯電話不感地帯での利用
携帯電話の不感地帯で行う工事などでも、近年は建設DXで利用するIoTセンサーの利用にインターネットと接続したネットワークが必要になる場合があります。そのため、例えばインターネット回線は衛星通信のスターリンクを導入して、建設現場には長距離無線LANを整備して繋ぐことで、建設DXや鉱山等でのIoTセンサーを利用することも可能です。
3-4.農業生産の遠隔からの管理での利用
農場での農作物の生育状況や盗難被害の防止を目的としたネットワークカメラの利用に広域をカバーできる長距離無線LANを導入して活用することもできます。管理者も場所を選ばす生育状況の管理を遠隔から行うことも可能です。まさにスマート農業の入口としても利用することができます。
3-5.地方河川での水位計測での利用
地方の河川など携帯電話の電波不感地帯で水位計測を行う必要がある場合にも、水位計測機器と例えば事務所間を長距離無線LANで結ぶことで水位の遠隔監視を行うことも可能です。水位計測を行う場所に電源が簡単に引けない場合にはソーラーパネル等を組み合わせて利用することもできます。
3-6.IoT機器向けで利用している既設のWi-Fi機器のリプレイスに利用する
既に防犯カメラやIoT利用向けで工場や公共施設内にWi-Fiを設置している場合に、既存のWi-Fiが老朽化した際のリプレイスにも長距離無線LANは利用することができます。電波が長距離に飛びなおかつ920Mhz帯を使うため電波が障害物を回り込みやすいメリットがあります。こういった特性があるため一般的なアクセスポイントから長距離無線LANのアクセスポイントへ移行することで、機器自体の数も減らしてコストダウンを図ることができます。接続機器側がIEEE802.11ah規格に対応していないことも十分考えられますがその際は接続機器と長距離無線LANのアクセスポイントをLANケーブルで接続することでこの問題を回避する方法もあります。
4.長距離無線LAN(IEEE 802.11ah)のメリット
ここでは長距離無線LANのメリットをご案内いたします。
4-1.長距離通信が可能
従来の一般的な無線LANでは100m程度の通信距離となるところを、1km前後まで通信範囲を広げることができます。日本でのIEEE802.11ah規格の仕様上、送信に使える時間の上限が通信全体の10%以内にする電波法の規制の中での利用となりますが、長距離通信のメリットを活かしつつIoT機器を中心に利用することができます。
4-2.消費電力を低く抑えることができる
この長距離無線LANは、LPWA(Low Power Wide Area)という従来よりも少ない電力で通信できる規格を採用しているため、接続機器側も少ない消費電力で通信を行うことができます。長距離無線LANを使うことで電池で稼働するIoT機器の場合は電池の消耗を遅らせることにつなげられます。
4-3.ランニングコストが不要
1km近い通信距離がある中で無線通信を行うとなると、長距離無線LANを選択するかSIMカードを使った携帯電話の通信網への接続を選択するかを比較することになります。長距離無線LANであれば初期費用はアクセスポイント代が(必要なら工事費も)必要となりますが、携帯電話の通信網でかかってくる月額費用は削減することができます。接続端末が多かったり、今後増えたり、長期間にわたって運用する場合は、ランニングコストがかからないため携帯電話の通信網の利用よりも安くすることも可能です。
5.長距離無線LAN(IEEE 802.11ah)の課題やデメリット
ここでは長距離無線LANの課題やデメリットをご案内いたします。
5-1.送信時間に制限がある
電波干渉を避けるため電波法により、長距離無線LAN(IEEE 802.11ah)の送信時間には全体の通信時間の10%以内となるよう制限が課されています。これは日本の法令での規定です。IEEE 802.11ah規格について諸外国では特にこういった制限は無いとも言われています。
5-2.通信速度が他のWi-Fi規格に比べて遅い
一般的に利用されているWi-Fiに比べて長距離無線LANのIEEE 802.11ah規格を利用したWi-Fiは通信速度が遅いというデメリットがあります。一般的なWi-Fiであれば実効速度で数十Mbpsは出るところ、長距離無線LANでは数Mbps程度に速度が落ちてしまいます。
5-3.対応機器がまだ少ない
ここも課題となりますが、IEEE 802.11ah規格に対応した機器が少ないということもあげられます。どうしても新しい機器がIEEE 802.11ah規格に対応して登場してくるのを待たなければいけない問題ではありますが、接続機器側にLANポートがあればアクセスポイントのLANポートと接続することで機器側の無線LANカードがIEEE 802.11ah規格に対応していない場合でも、長距離無線LANの通信を利用することができます。
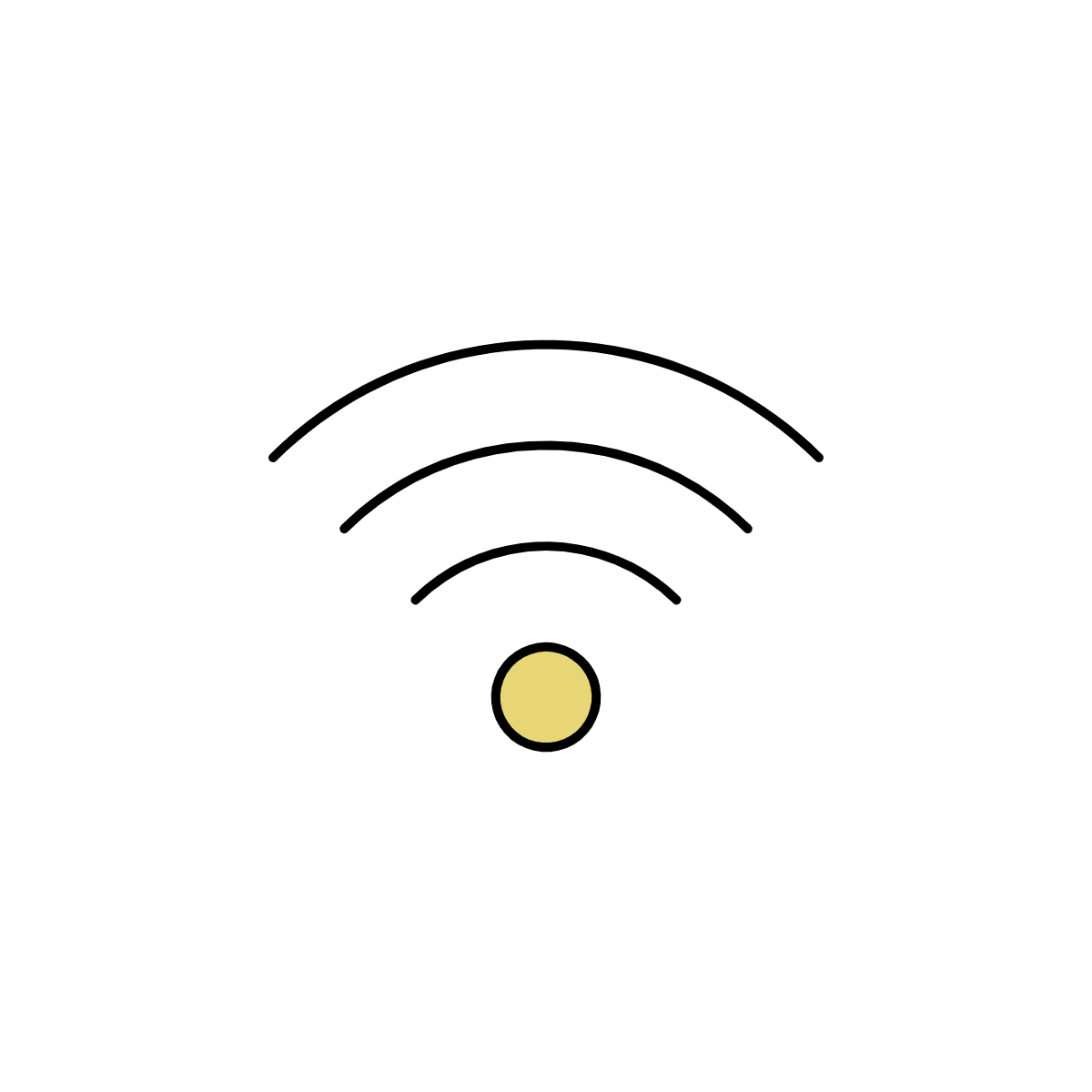
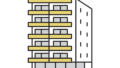

コメント